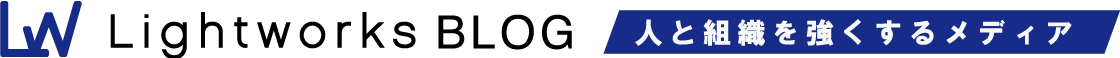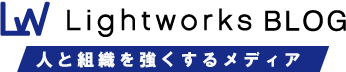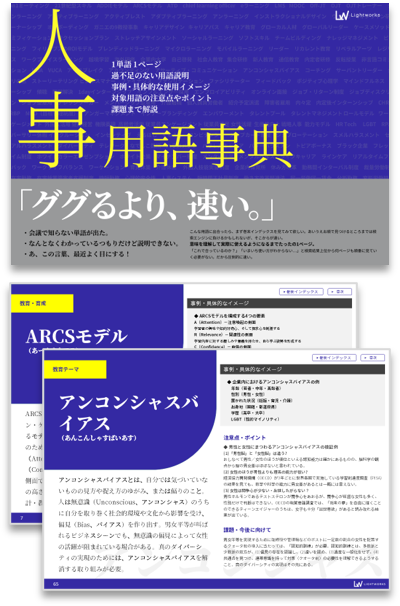「これからの時代、雇用や組織運営においてワークライフバランスが重要だということは理解しているが、新型コロナウイルスで従業員の働き方は大きく変わった。改めてどのように進めていくか考える必要がある」
このようにお考えのマネジャーや人事部門の方は多いのではないでしょうか。
ワークライフバランスという言葉は、すでに社会に広く浸透しています。採用シーンでも、新卒・中途限らず、必ずと言ってよいほど「ワークライフバランスは実現しやすいか」が入社検討材料の一つになりました。
しかし、言葉が普及したからといって本当に実現されているとは限りません。特に、新型コロナウイルス禍によって働き方が大きく変わった今、企業はワークライフバランスの在り方について改めて検討する必要があるでしょう。
そこで本稿では、今さら聞けない「ワークライフバランスとは」をテーマに、改めてワークライフバランス実現企業として取るべき施策をご紹介するとともに、今後のwithコロナ時代に合わせた新たな制度について考えます。ぜひ参考にしてください。
「ワークライフバランス」以外にも、「ARCSモデル」や「エンプロイアビリティ」など、近年話題の人事系キーワードについて詳しく知りたい場合は、163の用語を解説している「人事用語事典」をご利用ください。
⇒ダウンロードする
目次
1. ワークライフバランスとは
働き方改革の推進に合わせて、2000年以降「ワークライフバランス」という言葉が頻繁に使われるようになりました。まずはその背景や言葉の定義など改めてご紹介します。
1-1. ワークライフバランスの定義
内閣府によると、ワークライフバランスとは「仕事と生活の調和」と定義されています。つまり、仕事と生活のバランスが取れている状態をいいます。
これを提唱した内閣府の専用サイトでは、仕事は暮らしを支える重要なものだが、それと同時に育児や家事といった生活も暮らしに欠かすことのできないものとし、仕事と生活の調和の実現は、一人一人が望む生き方ができる社会の実現にとって必要不可欠と訴えています。
内閣府はワークライフバランスに関して強いリーダーシップを発揮し、2007年12月に策定された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章[1]」・「行動指針」は社会全体を動かす大きなきっかけとなりました。
毎年発表される「仕事と生活の調和に関する調査研究報告書[2]」を見ても、その推進の進捗がよく分かります。
1-2. ワークライフバランスはなぜ大切なのか
では、ワークライフバランスはなぜ大切なのでしょうか。個人、企業・組織、そして社会全体にとってそれぞれ以下の理由が挙げられます。
個人にとっての必要性
長時間労働や休日出勤など、仕事に比重を置きすぎると、心身の健康被害につながる可能性があります。これは回避しなければなりません。また、男女の仕事・家庭への関わり方が時代とともに変化し、仕事以外の活動に責任を持つ時間が増えていることからも、多様な働き方が求められています。
企業・組織にとっての必要性
従業員のワークライフバランスの実現に積極的に取り組むことは、企業・組織の競争力アップにつながります。労働人口が減少する中で、いかに優秀な人材を獲得し、定着させるか、従業員のニーズをくみ取り、働き方の選択肢を提供することは極めて重要な企業戦略です。
社会全体にとっての必要性
人口の減少に歯止めがかからない今、労働力確保のためには、一人一人が健康に・幸せに、できるだけ長く働き続けられる環境づくりが必要です。ワークライフバランスは、働き方の多様性を認める活動の一環として、重要な役割を果たしています。
1-3. ワークライフバランスの観点での経営メリットと問題点
企業としてワークライフバランスに取り込むことは、経営面において次のようなメリットが期待できます。
- 優秀な人材が確保できる
- 従業員のモチベーション向上につながる
- 業務の効率化による生産性の向上とコスト削減
優秀な人材が確保できる
ワークライフバランス実現企業として認知されることで、企業のブランドイメージは上がります。従業員に対して柔軟な働き方を認めることで、優秀な人材を確保しやすく、また、離職率を下げることにつながります。
従業員のモチベーション向上につながる
従業員が理想のワークライフバランスを保てることで、仕事への意欲や企業に対するエンゲージメントが高まることが期待できます。また、職場の雰囲気も良くなることから、従業員の満足度アップにつながります。
業務の効率化による生産性の向上とコスト削減
長時間労働を避けるためには業務の効率化は必須です。企業と従業員双方がこのことに積極的に取り組むことで結果的に生産性が向上し、残業代や休日出勤手当などのコスト削減につながります。
一方で、次のような問題点も無視できません。
- 具体的な対策を打ちづらい
- 生産性が下がる可能性もある
- 定着させるまでの風土づくりに時間がかかる
具体的な対策を打ちづらい
仕事と生活の調和は、極めて従業員個人の考え方や生活スタイルに左右されます。また、企業の規模や業種、社風によっても取り得る策は異なり、マニュアル通りというわけにはいきません。何から着手していいのか分からないという人事担当者の声は少なくありません。
生産性が下がる可能性もある
ワークライフバランスによって業務の効率化を図ろうとしても、単に労働時間を減らすだけになってしまっては生産性が低下する可能性が高いでしょう。業務プロセスを大幅に改善するには、それなりの工数がかかります。
定着させるまでの風土づくりに時間がかかる
「残業をしなくてもいい」「家族を優先させてもいい」と言われても、すぐには定着しないかもしれません。労働時間で評価されてきた時代が長いだけに、従業員の意識を変えることは簡単なことではありません。
人事に関する注目トピックを毎週お届け!⇒メルマガ登録する
2. ワークライフバランス実現のために推進するべき5つのポイント
ワークライフバランス実現企業になるために、具体的に推進すべきことは何でしょうか。ここでは、従業員の多様かつ柔軟な働き方に対応するために取り組むべきポイントを5つご紹介します。
2-1. 休暇に関する制度
2019年4月から労働基準法が改正され、企業が従業員に年間5日の有給休暇を取得させることが義務付けられました。
企業側は積極的に休暇を取得させる必要があります。男女問わず育児休暇、介護休暇が取得可能であることはもちろん、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇など、法令で定める日数以上に休暇を取得できるよう、選択の幅を広げておくとよいでしょう。
また、有給休暇の失効分を積み立てられる「ストック休暇」も有効です。ワークライフバランスのために堂々と休暇が取れる切り札として、あるべき制度といえるでしょう。
2-2. 労働時間に関する制度
ワークライフバランスと労働時間の短縮は、常にセットで議論されます。長時間労働を防ぐためにすべきことは、以下が挙げられます。
・従業員の1カ月当たりの労働時間を把握する
・どの業務にどれだけの時間がかかっているのかを可視化する
・長時間労働に陥っている従業員や部署を特定し、改善策を検討する
特に長時間労働の実態がある場合、業務過多であれば業務フローの見直しを、ダラダラ勤務が原因の場合は残業を承認方式に変えるといった取り組みを実施することが有効です。メンバーの労働時間や成果をマネジャーが把握し、人事や経営側にフィードバックする仕組みをきちんと回しましょう。
また、労働時間に関して相談できる窓口を設けることも重要です。これにより、「定時で帰りにくい」などの不満を減らし、ワークライフバンスを大切にする風土が育ちやすくなるでしょう。
2-3. 取り組みを可視化する
労働時間や業務内容などを可視化することは、ワークライフバランスの推進においてとても有効な手段です。ライフの方の割合を増やしたいときに、ワークの方にどのような工夫をすればよいかが分かりやすくなるためです。これは、生産性の向上にもつながります。
可視化に当たっては、何をどのように可視化するのか、ルールを決めることから始めましょう。
働き方を可視化していくことは、レコーディングダイエットに例えられることがあります。自分の仕事を記録することで、業務の無駄に気付き、意識して改善することができるのです。
また、チーム・組織ごとに取り組みを可視化する方法も有効です。分担に偏りがないか確認することもできますし、全体目標を改めて確認し、協力して進めていく体制を整えることにもつながります。
2-4. 評価制度の見直し
ワークライフバランスの推進においては、評価制度の見直しも必要となるでしょう。実績評価に加えて、「業務を改善して無駄をなくした」「アウトソーシングで自身の負荷とコスト削減に成功した」など、ワークライフバランスの取り組みに関連する項目について評価を加えることを検討してみてください。
昨今取り入れる企業が増えている「360度評価[3]」も、ワークライフバランスの観点で有効な評価制度の一つといえます。
2-5. タイムマネジメントの重要性
仕事においても生活においても効率性が求められるワークライフバランスで、重要になる能力がタイムマネジメントです。
今日やるべきことは何か、そのための手順は何か、優先順位付けをしながら決めた時間内で成果を出すことを目標にします。これは従業員に求められる能力であり、企業が積極的に指導して習得させるべき能力なのです。
タイムマネジメントの強化に当たり、始めやすいのはいわゆる日報です。具体的には、メールや複数のメンバーで共有できるコミュニケーションツールを用い、その日の業務予定や業務内容を報告します
その日の業務が把握できてスケジュールに落とし込むことができているか、手順は正しいか、どのように業務を行って成果の振り返りができているかなどの一連の流れを、上長やメンバーが把握できるようにすることが重要です。
タイムマネジメントスキルに関しては、集合研修やeラーニングでも学ぶことができます。例えば、当社製のeラーニングには、タイムマネジメントや長時間労働の是正をテーマにしたものがあります。
タイムマネジメントの教材では「労働時間」について時短へのアプローチ方法や、タイムマネジメントスキルとして「自分が処理可能な仕事量をコントロールする方法」などについて学ぶことができます。
これをLMS(Learning Management System: 学習管理システム)である「CAREERSHIP®」で配信することで、全ての従業員に同じ学習内容を届けることができます。効率の良さはもちろんですが、タイムマネジメントや長時間労働について全社的に同じ認識を持てること、風土づくりに役立つ点も大きなメリットです。
>>eラーニング「タイムマネジメント」についてもっと知りたい方はコチラ
>>eラーニング「チームで取り組む長時間労働の是正」についてもっと知りたい方はコチラ
3. ワークライフバランス実現企業の事例
「仕事と生活の調和」推進サイト(内閣府)では、ワークライフバランス実現企業としていくつかの事例が紹介されています。企業規模や業種は異なれど、ワークライフバランスの実現で成果を上げていることが分かり、今後の取り組みに見通しを付ける参考になるでしょう。
企業名 | 取り組みの概要 | ワークライフバランスポイント |
有限会社 | 慢性的な長時間労働や退職者の発生などを解決 | ・妊娠中や産休復帰後の女性従業員のための相談窓口設置 |
旭化成株式会社 | 男性の育児参加を後押しする | 男性従業員の育児休業取得に関して以下を制度化 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 「両立支援」「能力発揮」「意識改革・風土づくり」の3本柱で推進 | ・事業所内保育所の設置 |
4. withコロナ時代のワークライフバランス
ここまで、ワークライフバランスとは何か、メリットや問題点、取り組むべきポイントをご紹介してきました。今では決して新しくはない言葉ですが、昨今の新型コロナウイルス禍において再び注目を浴びています。
新型コロナウイルス禍で明らかになったこと、それはリモートワークに代表されるように、企業が働き方の多様性を認めることは必須ということです。
先述の5つのポイントも参考にしながら制度や業務の見直しを行い、持続的にワークライフバンスが実現可能な企業になることが、競争力を高めることにつながります。
経営サイドの検討事項として、「令和元年度 仕事と生活の調和推進のための調査研究 エグゼクティブ・サマリー[4]」の「職場に関すること」の項目が参考になります。
例えば、男性の育児と仕事の両立上の課題としては、「職場での両立中の男性の不在」「労働時間の長さ」などが挙げられています。また、「時間単位、半日休暇など、柔軟な有給休暇の取得が両立に有効」という調査結果も示されており、自社でアンケートを取ってみるのも有効な手段でしょう。
さらに、柔軟な働き方を認めるとともに、メンタルケアにも気を配らなければなりません。新型コロナウイルス禍で急増したリモートワークについては、従業員の孤独感、ストレス増加への対処が新たな課題[5]となりました。
企業はできるだけ選択肢を増やして従業員の生活の充実をサポートし、従業員は心身の健康を得、仕事で良いパフォーマンスを発揮します。この正のスパイラルを双方が意識し、ワークライフバランスを追求していくことが大切です。
統合型学習管理システム「CAREERSHIP」

クラウド型LMS 売り上げシェアNo.1 *
21年以上にわたって大企業のニーズに応え続けてきたライトワークスが自信を持ってご紹介する高性能LMS「CAREERSHIP」。これがあれば、「学習」のみならず人材育成に係る一連のプロセスを簡単に管理することができます。ぜひお試しください。
*出典:ITR「ITR Market View:人材管理市場2025」LMS市場:ベンダー別売上金額シェア(2024年度予測)
5. まとめ
ワークライフバランスは「仕事と生活の調和」と定義されています(内閣府)。つまり、仕事と生活のバランスが取れている状態をいいます。
ワークライフバランスは個人、企業・組織、社会それぞれにとって必要であり、内閣府によって「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」が策定されるなど、社会全体で取り組んでいくべき課題であると認知されています。
今回は主に企業にとってのワークライフバランスの必要性を取り上げました。経営メリットとしてご紹介したのは以下の3点です。
1. 優秀な人材が確保できる
2. 従業員のモチベーション向上につながる
3. 業務の効率化による生産性の向上とコスト削減
一方で、次のような問題点も取り上げました。
1. 具体的な対策を打ちづらい
2. 生産性が下がる可能性もある
3. 定着させるまでの風土づくりに時間がかかる
ワークライフバランス実現のために推進するべき5つのポイントをご紹介しました。自社に合わせた取り組みを検討し、ワークライバランス実現企業として企業競争力を高めましょう。
1. 休暇に関する制度
有給休暇の失効分を積み立てられる「ストック休暇」が有効
2. 労働時間に関する制度
メンバーの労働時間を管理職が把握し、人事や経営側にフィードバックする仕組みをきちんと回すことが大切
3. 取り組みを可視化する
労働時間や業務内容などを可視化し、常に業務改善を意識付ける
4. 評価制度の見直し
実績評価に加えてワークライフバランスの取り組みに関しても評価を加えるとよい
5. タイムマネジメントの重要性
業務の効率化に求められるのは「タイムマネジメント能力」。スキルアップにはeラーニングの活用も有効
新型コロナウイルス禍において、これからは企業が働き方の多様性を認めることが必須であると明らかになりました。その大きな柱になるのがワークライフバランスです。
ワークライフバランスの実現においては、企業も従業員も、効率性と生産性を高めることが求められます。
企業はできるだけ選択肢を増やし、従業員の生活の充実をサポートします。従業員は生活が安定することで、心身の健康を得、仕事で良いパフォーマンスを発揮します。この正のスパイラルを双方が常に意識することが大切です。
ワークライフバランスは、企業と従業員の双方が協調しながらつくっていくものといえるでしょう。
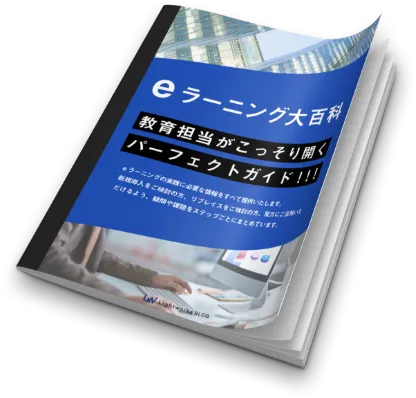
社員教育や人材開発を目的として、
・eラーニングを導入したいが、どう選んだらよいか分からない
・導入したeラーニングを上手く活用できていない
といった悩みを抱えていませんか?
本書は、弊社が20年で1,500社の教育課題に取り組み、
・eラーニングの運用を成功させる方法
・簡単に魅力的な教材を作る方法
・失敗しないベンダーの選び方
など、eラーニングを成功させるための具体的な方法や知識を
全70ページに渡って詳細に解説しているものです。
ぜひ、貴社の人材育成のためにご活用ください。
プライバシーポリシーをご確認いただき「個人情報の取り扱いについて」へご同意の上、「eBookをダウンロード」ボタンを押してください。
[1]内閣府,「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」,『「仕事と生活の調和」推進サイト』,http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/20barrier_html/20html/charter.html
[2]内閣府「仕事と生活の調和推進のための調査研究~多様で柔軟な働き方推進に向けた企業の取組に関する調査~報告書」,2023年3月公表,https://wwwa.cao.go.jp/wlb/research/wlb_r0503/1.pdf
[3] 対象者に対し、あらゆる角度(上司、同僚、部下など)から評価すること。現在、多くの企業で導入されている評価方式で、人事考課だけでなく人材育成や組織活性化などにも活用されている。
[4] 内閣府「令和元年度 仕事と生活の調和推進のための調査研究 エグゼクティブ・サマリー」, https://wwwa.cao.go.jp/wlb/research/wlb_r0103/1.pdf
[5]PR TIMES「「テレワークの方が従業員のメンタルケアが難しい」が7割超。半数以上の総務がテレワークの推進でストレスが増えたと実感」, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000060066.html