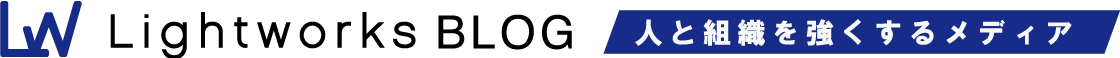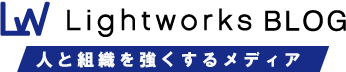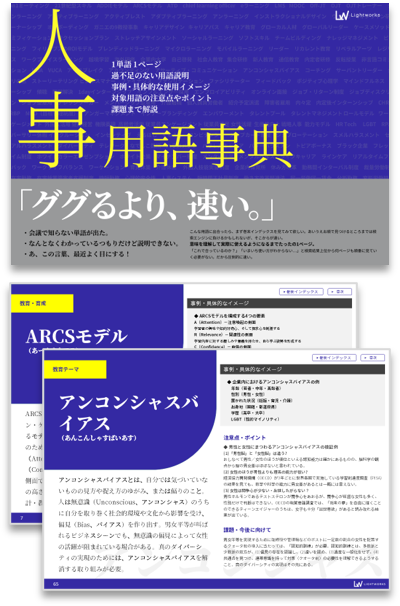テレワークとは、情報通信技術(ICT=Information and Communication Technology)を活用した、時間や場所を選ばない柔軟な働き方のことです。パソコンやスマートフォン、タブレットなどの端末を用い、インターネットを使ったサービスやシステムを利用して、会社のオフィスではなく自宅やサテライトオフィスなどで業務をするスタイルを指します。
「働き方改革」「ワークスタイル変革」が叫ばれていますが、その目的は生産性の向上、優秀な人材の確保、イノベーションの創出。これらを実現するための具体的な施策の一つが雇用形態の多様化です。そうした流れの中でテレワークが注目されているのは、介護や育児のために会社で働くことができない、遠隔地で通えないなどの人材を活用していくことができるからです。
この「テレワーク」にはどんなメリット(効果)があり、どんなデメリット(課題)があるのでしょうか。本稿では、それらを解説するとともに導入企業の取り組み事例を合わせて紹介していきます。
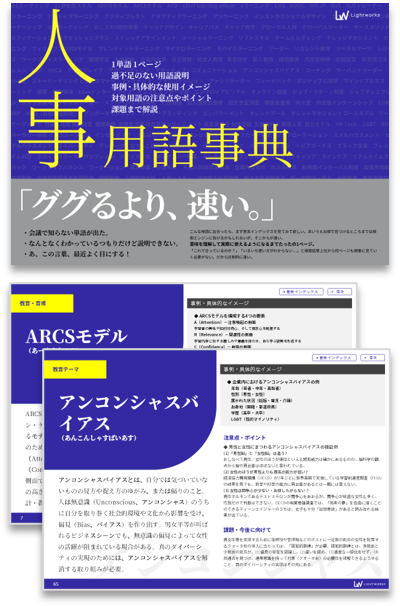
ライトワークスブログに掲載された記事からピックアップした企業の人事に関連する163の用語が収録されています。
以下6つのカテゴリに用語を分類し、検索しやすいようまとめています。
- 教育・育成
…ARCSモデル、アクションラーニング など - 教育テーマ
…アンコンシャスバイアス、サーバントリーダーシップ など - 採用・雇用
…インフルエンサー採用、エンプロイアビリティ など - 人事企画
…健康経営、従業員エンゲージメント など - 制度・環境の整備
…インクルージョン、ピアボーナス など - 労務管理
…がんサバイバー、36協定 など
ぜひ様々なシーンでお役立てください。
目次
1. テレワークとは
テレワークとは、「離れた」という意味を持つ「テレ(tele)」と、「仕事」という言葉の「ワーク(work)」を組み合わせた造語で、ICTを活用した、時間や場所を選ばない柔軟な働き方のことです。
なぜテレワークが注目されるようになったのでしょうか。その背景には、企業を取り巻く経営環境が大きく変化しているという現状があります。
・少子高齢化の進展に伴う労働人口の減少、人材確保の難しさ
・グローバル化の進展による企業間競争・国際競争の激化
これらの課題に対応していくためには、経営の効率化や優秀な人材を確保するための働き方の変革が必要です。一方、ICTの発達によって、それが可能になったともいえるでしょう。
総務省の通信利用動向調査(2015年)によると、テレワーク導入企業は確実に増加し、2016年に毎日新聞が実施した主要121社への独自調査では、「在宅勤務を導入している・導入を決めている」が48%、「在宅勤務の導入を検討している」が25%という結果がでています。政府が2016年から取り組んでいる「働き方改革」においても「テレワークの推進」は重要施策として位置づけられています。
テレワークは、働き方や働く場所によって次のように分類できます。
① 雇用型(企業に勤務する被雇用者が行うテレワーク)
・自宅利用型(在宅勤務):出勤せず、自宅で仕事をする
・モバイルワーク(外勤型):PCやスマホなどを活用して仕事をする
・施設利用型:サテライトオフィス、テレワークセンター、スポットオフィスなどに行って仕事をする
② 自営型(個人事業者・小規模事業者が行うテレワーク)
・SOHO、ノマドワーカー:主に専業性が高い仕事をする。独立自営の度合いが高い
・内職副業型(在宅ワーカー):主に他のものが代わって行うことが容易な仕事をする。独立自営の度合いが低い
一般に「テレワーク」というと従業員が企業の業務をオフィス以外の場所ですることというイメージがありますが、個人事業者の仕事を指すこともあります。
2. テレワークのメリット
テレワーク導入により、企業と従業員には次のようなメリットが生まれます。
企業
・優秀な人材の確保と定着につながる
・生産性が向上する
・オフィスコストが削減できる
・従業員重視という企業イメージ向上につながる
従業員
・介護や育児などをしながら働ける
・通勤に時間がとられない分、時間を活用できる
・家事と仕事の両立がしやすくなる
テレワークは、柔軟で多様な働き方を実現するだけでなく、働き手の間口を広げ、眠っている人材を活用することができます。
また、「ワーク・ライフ・バランス」の実現という点からも効果的といえます。
3. テレワークのデメリット
一方で、導入にあたっては次のような課題もあります。
企業
・従業員の勤務実態が見えづらい
・情報漏えいリスクが増える
・直接・対面での人材育成ができない
・従業員の企業への帰属意識が希薄になる
従業員
・時間の自己管理が必要
・長時間労働につながる懸念
・社内コミュニケーション機会の減少
テレワークを導入する際には、これらの課題を事前に把握しておく必要があります。既存の制度を見直す必要があるのか、どのような対策を講じるべきか、あらかじめ検討をしておくことが重要です。
4. テレワーク導入企業の取り組み
テレワークの導入はどのくらい進んでいるのでしょうか。
国土交通省が発表した「テレワーク人口実態調査(2016年度)」によれば、勤務先にテレワーク制度があるという回答は雇用者全体のうち14.2%でした。また、総務省の発表によると、資本金50億円以上の企業のテレワーク導入率が13.6%であるのに対し、資本金1000万円未満の導入率は1.2%に留まっています。
現在では、日本マイクロソフト、日立製作所、トヨタ自動車、日産自動車、日野自動車、ローソン、日本マクドナルド、住友林業、明治安田生命、東京海上日動、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、カルビー、サントリー、ベネッセ、リクルートなど、業種によらずさまざまな企業がテレワークの制度を導入しています。
これらの企業から、いくつかテレワーク導入事例をご紹介します。自社で導入を検討するのに役立ててください。
4-1. 日産自動車 男性の在宅勤務を大幅に増加
日産自動車では、2006年に育児・介護を目的とした在宅勤務制度を導入しました。その後、将来共働きの従業員が増加すると、従来の勤務制度では働く時間に制約ができてしまう従業員が増えると想定されるようになりました。このため制度運営を見直す際、課題を把握し、トライアルを経て2014年1月より生産部門以外の全社員を対象に在宅勤務を本格導入しました。
実施に当たっては、在宅勤務希望者は制度利用のためのeラーニングを事前受講し、在宅勤務の前日までに在宅時の業務計画について上司と合意。在宅勤務時の業務内容を職場内で共有しています。在宅勤務日は、上司に業務開始と終了をメールで報告するとともに、システムの活用により在宅状況を同僚に通知できるようにしています。
同社の在宅勤務には次の形態があります。
・一般形在宅勤務
日数制限はなく、30分単位で部分在宅が可能(月40時間が上限)。フレックスタイム制度 との併用により柔軟な働き方を実現しました。
・育児・介護型在宅勤務
所定内の労働時間の50%まで可能。
時間や日数の選択肢を広げ、柔軟な働き方を可能にしたことで、男性の利用が倍増しました。2015年度の在宅勤務制度利用は約22,000人の従業員のうち管理職を含めて約4,000人という実績が出ています。
4-2. 明治安田生命保険 管理職からの実践が効果的
明治安田生命保険は、育児・介護を担う従業員以外にも在宅勤務制度を適用。従業員一人ひとりのワーク・ライフ・バランスを促進し、多様な働き方を認めることによって優秀な人材を確保することを目指しテレワークを導入しています。
テレワーク導入の目的の一つは、育児・介護によって仕事の能力の向上や昇進に支障が出ないようにするためとされています。営業職の従業員約3万人を対象にタブレット端末を貸与し、顧客先で、保険プランの案内をする場合などに有効活用しています。また、プレトライアル開始以前からBCP(事業継続計画)対策として、本社に所属する従業員のうち一部を対象にテレワークができるシステムを導入しています。
実施に当たり、2015年1月にプレトライアルを開始し、利用者アンケートを実施。同年4月に本社全組織に拡大し、同年7月時点からは約1300人を対象に自宅用の私用パソコンを活用した試験を行いました。2016年からは約2000人を対象としています。
導入効果については、「在宅勤務を利用したい」約95%、「業務の効率化を実感」約85%、「働き方の改革につながると感じた」約80%、「部下の在宅勤務制度の利用に肯定的な管理監督者」約80%と、高い成果を出しています。
4-3. リクルートマネジメントソリューションズ インプット(学習)のための時間を確保
リクルートグループでは、各社で独立した経営を行い異なる制度を運用していますが、全体として積極的にテレワークに取り組んでいます。
リクルートマネジメントソリューションズは、2013年10月より会議運営の効率化、資料作成のフォーマット化などさまざまな方策と並行し、単位時間当たりの業務生産性向上を実現する一つの支援策としてテレワーク制度を全社に導入しています。
経営サイドは、全従業員に対してプロフェッショナルとしての専門性を高めることを求め、人事制度の刷新を行いました。この中でインプット(学習)のための時間を確保し、高い成果へとつなげることを目的に労働時間の短縮、生産性の向上を狙ったテレワーク制度の新設を決定しました。
同社のテレワーク制度には次の二つの形態があります。
・1日在宅型
自律的に業務を進めることができると認められている一定等級以上の従業員に限定されていますが、週2日を上限として利用できます。
・直行前・直帰後型
営業やコンサルティング担当などの外出を前提とする業務の従業員は日数制限なし、オフィス勤務が前提の従業員については週2日を上限に利用可能です。自宅から直接顧客企業へ向かう前、もしくは顧客先からの直帰後に、メールのやり取りや企画書の作成といった業務を自宅で行うことができます。
同社では、テレワーク制度を利用する従業員の約8割が「生産性が向上した」と回答。2017年4月からは育児、介護、病気、けがなどの事由がある場合は、職種や等級、日数の制約なしで利用できるように制度が拡充されました。
統合型学習管理システム「CAREERSHIP」

クラウド型LMS 売り上げシェアNo.1 *
21年以上にわたって大企業のニーズに応え続けてきたライトワークスが自信を持ってご紹介する高性能LMS「CAREERSHIP」。これがあれば、「学習」のみならず人材育成に係る一連のプロセスを簡単に管理することができます。ぜひお試しください。
*出典:ITR「ITR Market View:人材管理市場2025」LMS市場:ベンダー別売上金額シェア(2024年度予測)
5. まとめ
テレワークとは、ICTを活用した、時間や場所を選ばない柔軟な働き方のことです。
企業、従業員各々のメリット・効果とデメリット・課題には次のようなことがあります。
| 企業 | 従業員 |
メリット | ・優秀な人材の確保と定着 ・生産性の向上 ・オフィスコストの削減 ・従業員重視という企業イメージ向上 | ・介護や育児などをしながら働ける ・通勤時間の削減による時間の活用 ・家事と仕事の両立 |
デメリット | ・従業員の勤務実態が見えづらい ・情報漏洩リスクの増大 ・直接・対面での人材育成ができない ・従業員の企業への帰属意識の希薄化 | ・時間の自己管理が必要 ・長時間労働につながる懸念 ・社内コミュニケーション機会の減少 |
大企業での導入が進む一方で中小企業での導入率はまだ低いのが実態です。
しかし、労働人口が減少する中で、柔軟な働き方やそれに対応する制度を企業が整え、多様な人材を積極的に活用していくことは企業競争に生き残っていくためにも必須と思われます。
この機会に、テレワーク制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
参考)
日本テレワーク協会 テレワークとは
http://www.japan-telework.or.jp/intro/tw_about.html
総務省 テレワークの意義・効果
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/18028_01.html
TELEWORKERS 実例から学ぶ!テレワーク導入好事例3選
http://teleworkers.style/case-study/529/
国土交通省 都市局 都市政策課 都市環境政策室 テレワーク実施におけるワーカーの課題に対する企業の取組~ヒアリング調査結果の概要~
http://www.mlit.go.jp/crd/daisei/telework/docs/29telework_kigyouhiaringu.pdf