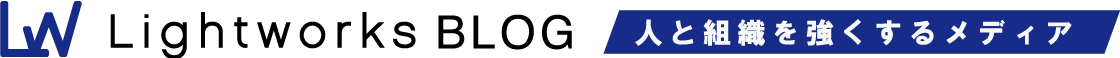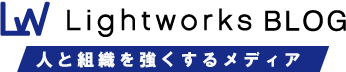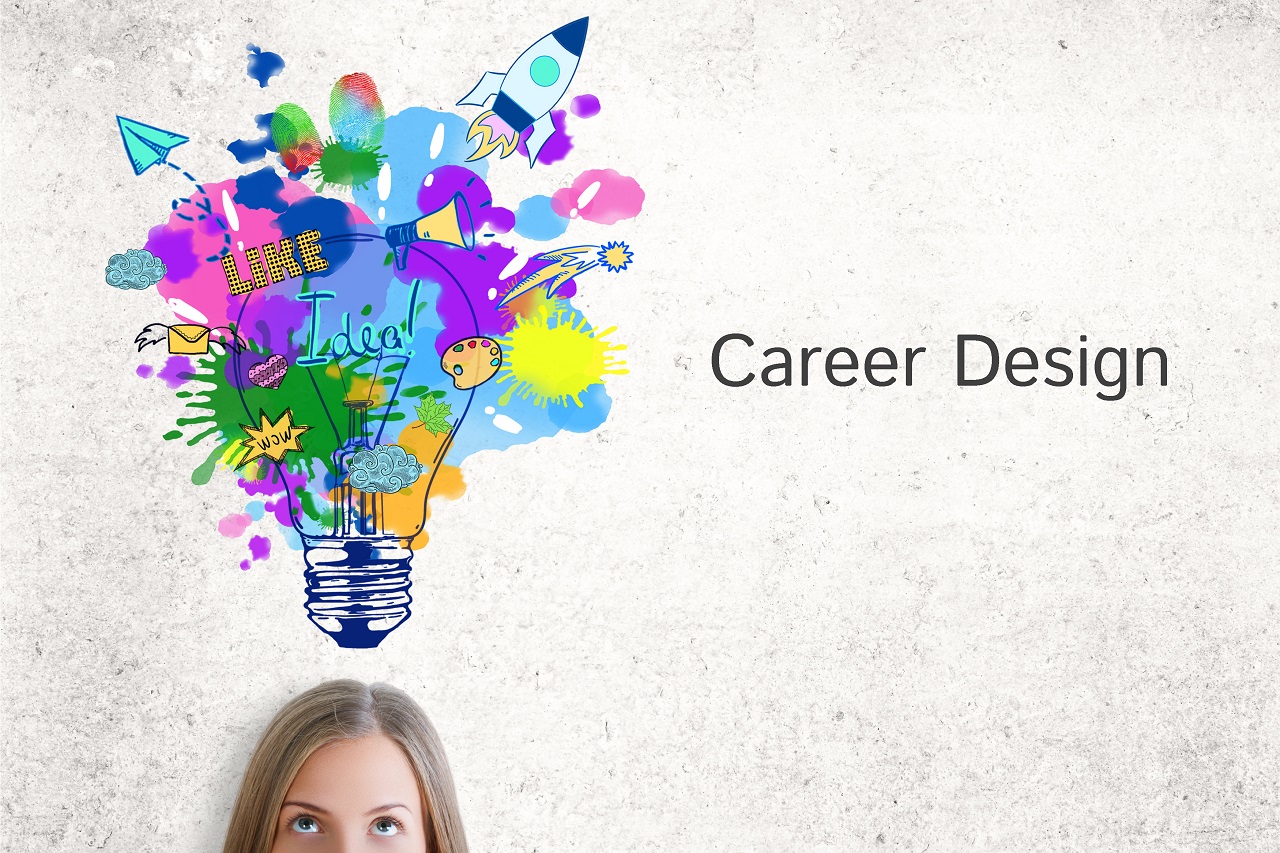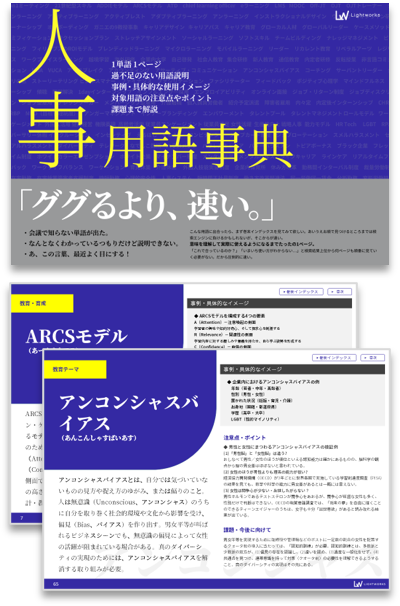「ヒトの問題はデリケートで気苦労が絶えない」
このようにお感じになっているリーダーの方は多いのではないでしょうか?
業績に責任を負っているリーダーにとって、業績が一番の関心事であることは間違いありません。ところが、業績はヒトによって実現されます。ヒトに問題があったら、業績目標を達成することは困難でしょう。ヒトの問題を解決することができて、初めて業績の問題も解決することができると言えます。
したがって、ヒトに関する問題解決のスキルを磨くことはリーダーにとって非常に重要な意味を持つことになります。
本稿では、ヒトの問題に関してリーダーに求められる問題解決のスキルについてわかりやすく説明します。
「問題解決の極意」以外にも、「ARCSモデル」や「エンプロイアビリティ」など、近年話題の人事系キーワードについて詳しく知りたい場合は、163の用語を解説している「人事用語事典」をご利用ください。
⇒ダウンロードする
目次
1. 問題を解決するとはどういうことか?
最初に取り上げるのは、そもそも「問題を解決するとはどういうことか」という課題です。
職場では朝から晩まで様々な問題が大量に発生しています。リーダーの方はそのような問題を次々と解決しています。問題を解決できなければ職場を回すことはできません。したがって、リーダーの方には問題解決のスキルが十分に備わっていると言えます。
ところが、時として解決するのに苦労する問題に直面します。問題解決のスキルがあるはずなのに、なぜ解決できないことが起こるのでしょうか。ここに問題解決についてのヒントがあります。
リーダーの方が多種多様な問題を解決できる理由は、同じような問題を過去に解いた経験があるからなのです。だからこそ瞬時の判断で問題を解決できるのです。そうすると、問題解決は、「過去に似たような問題を解決したことはないか」というのが基本戦略となります。
この基本戦略に従えば、自分の経験を振り返ることが問題解決の王道となります。「経験がものをいう」と言いますが、ヒトの問題解決では間違いなく経験が頼りになります。
しかし、個人の経験には限界があります。そこで、すでに類似の経験をした人に教えてもらうという打ち手を考えることができます。ここに先輩や専門家の存在意義があります。さらに、人々の様々な経験(事実、現象)から帰納的に導いた一般的原理が理論になるので、ヒトに関する理論を活用するという手も考えられます。
しかしながら、ビジネスというのは誰も見たことのない未知なる未来への挑戦です。そのため、経験したことのない問題に直面することはどうしても避けられません。そのときにどうすればよいでしょうか。これが問題解決における本質的な課題になります。したがって、経験を活用できないときでも対応できる普遍的な問題解決のスキルが求められることになるのです。
人事に関する注目トピックを毎週お届け!⇒メルマガ登録する
2. ヒトの問題とは何か?
普遍的な問題解決のスキルを論じる前に、「ヒトの問題」とは何かということを見ておきましょう。
「あいつは使えない。期待していたけど、がっかりだ」
「まだまだ物足りない。彼女にはもっと頑張ってもらいたい」
ヒトの問題というと、このようなイメージを持つ方もいると思います。これもヒトの問題に相違ありませんが、このような乱暴な捉え方では、とても問題を解決することは期待できません。なぜなら、「使えない」というのは具体的に何を意味しているのか。何を証拠に「使えない」と判断したのか。「物足りない」ケースと「満足している」ケースを分けるボーダーラインは何か。何ができたら「頑張った」ことになるのか。このようなシンプルな質問にも答えられないからです。
ヒトに対する否定的な評価は、その人の人生に大きな影響を与えます。そのインパクトの大きさに比べて、著しくバランスを欠いた問題認識と言わざるをえません。
そもそもヒトが問題になるのは、それが業績と直接的に関係するからです。ヒトに問題があっても業績で目標を達成すればよいという意見もあるでしょうが、それは神風が吹いたときだけに発生する現象です。神風が吹き続けることは決してありません。
そうすると、ヒトの問題というのは、正確にはヒトのパフォーマンスの問題ということになります。ヒトのパフォーマンスに対してどのようにアプローチすればよいか。これがヒトの問題の課題ということになります。
次に、ヒトの問題の「問題」のほうに注目してみましょう。問題というのは、一般的に、あるべき姿と現実のギャップのことを指します。そうすると、ヒトの問題というのは、期待されるパフォーマンス(これをShouldと呼ぶことにします)と実際のパフォーマンス(これをActualと呼びます)のギャップということになります。
ヒトの問題を論じるためには、期待されるパフォーマンスのレベルであるShouldが明確に設定されていることが大前提になります。さらに、Shouldが上司と部下の間で共有される必要があります。Shouldなしに仕事をするのは、バーを掛けずに棒高跳びをするようなものと言えます。
例えば、社内の他部署からAさんが部下として異動してくるというケースを考えてみましょう。最近では外部から採用するケースも多いことでしょう。この場合、Aさんに対して1か月後に期待されるパフォーマンスのレベルを規定しているでしょうか。この1か月で提供するトレーニングと実務経験はこれとあれ、その結果、1か月後には何と何ができるようになっていなければならない(Should)、ということです。
営業であれば、製品の基礎知識を習得するトレーニングを実施し、先輩と顧客訪問に同行させる。その結果、1か月後には定番商品の新規顧客への売り込みが1人でできるようになっている、という具合です。さらに、一人前になると想定するタイミングを決めて、それまでの期間は月ごとに到達すべきパフォーマンスのレベルが明確になっている必要があるでしょう。
試用期間がある外部採用の場合には絶対に必要な措置ですが、内部登用でも本質は同じはずです。一人前になった後も、人事評価やキャリアプランの時間軸に応じてShouldが明確になっている必要があります。
ヒトの問題の多くは、期待されるパフォーマンスであるShouldを明確に設定していないことに起因しています。Shouldが明確になっていないのに、「おまえは期待外れだ」と言われたら部下も困惑するだけです。何を目指して努力をしていいかもわからないので、ヤル気があってもうまく行きません。
残念ながら、筆者の知る限りにおいてShouldを丁寧に設定して部下に伝えているケース多くはないようです。
一方、実際のパフォーマンスを表すActualにも問題が生じます。それについては部下に対して否定的な見解を持つ上司に「否定的な評価を証明する証拠を挙げてほしい」と聞いてみるとわかります。評価そのものは適切だとしても、多くは印象のレベルに留まっていて、証拠として提出できる具体的な情報のリストにはなっていないというのが、これまでの筆者の印象です。
Actualの情報に問題が生じるのには2つの理由が考えられます。ひとつは、Shouldを明確にしていないためです。Shouldというガイドラインがあってこそ、それに対するActualが明確になります。Shouldがはっきりしていなければ、何に注目してActualの情報を追いかければよいかがわかりません。
もうひとつは、ヒトのActualの情報収集が難しいということです。モノを扱う製造現場では、生産量や品質といったパフォーマンスのデータ(Actual)の多くは自動的に記録できます。しかし、ヒトについてそうは行きません。意識的に努力しない限り高品質の情報は集まらないのです。
そのため、ヒトについては品質に問題のある情報が錯綜し、根拠の薄弱な噂話に基づいて「問題あり」と思ってしまうことも珍しくありません。
3. ヒトに関する問題解決は、一般的な問題解決と何が決定的に異なるのか?
問題解決の技法は、クリティカルシンキングや論理的思考という名の下に同工異曲のアプローチが紹介されていますが、そのルーツははっきりしています。それは17世紀のフランスの哲学者デカルト[1]の「方法序説」です。原題は「方法の論証」という意味で、何のための方法かは、その副題を見るとわかります。直訳すると「理性を適切に導いて、科学において真理を探究するために」となっています。
つまり、科学的に真理を見極める方法ということです。その方法として、デカルトは次の4つのアプローチを提唱しています。
- 正しいと認められるものだけを受け入れる(明証性の規則)
- 答えを得られるように問題をできるだけ小さく分解する(分析の規則)
- 最も単純なものから最も複雑なものへと思考を進める(総合の規則)
- 全体を把握しているか、モレがないかを確認する(枚挙の規則)
これが「要素還元主義」と呼ばれる考え方で、今日の科学の基礎となっているものです。問題解決には様々な技法があるように見えますが、要するに「科学的なアプローチでやりましょう」ということなのです。ヒトの問題は上司の直感や好みで決めることもできますが、それでは公平性を保てません。
上司の恣意的な判断に委ねるには、ヒトの問題はあまりにも重大です。ヒトの問題に対しては、あくまでも客観的で合理的な科学的アプローチで問題解決を図ることが望ましいと言えます。
科学的なアプローチは製造現場をはじめとしたエンジニアリングの世界でフル活用されていて、大きな成果を上げています。しかし、エンジニアリングが対象とするモノとヒトは同じではありません。ヒトはモノとは決定的に異なる存在です。そのため、科学的なアプローチでヒトの問題に切り込む場合には特別な注意が必要になります。
モノの場合は、欠点を指摘すればするほどよいことになります。それによって問題の原因が解明され、改善が進むからです。しかし、ヒトには自尊心があります。欠点を追及されたら誰だって心に抵抗を覚えます。その結果、改善が進まないということが起こります。ヒトが心を持った対象であることに留意して、常にリスペクトを持って相手に対応しなければなりません。
また、モノの問題についてはデータの収集が比較的容易です。不良率、燃費、生産性などの定量的データは採ろうと思ったらいくらでも採れます。しかし、ヒトについては、事実に基づいた情報を収集することは容易ではありません。モノの場合は過去に遡って生データを追いかけることができますが、ヒトはそういうわけに行きません。
どうしても「誰かがそう言っていた」、「そうするのを見たことがある」といった間接情報に頼らざるを得ない面があります。さらに、モノと違ってヒトの場合は噂話が横行する危険性が常にあります。それが偏見に結び付くことも珍しくありません。
4. なぜヒトに関する問題解決が特別に難しいのか?
以上の議論を踏まえて、ヒトの問題解決が難しい理由を改めて整理しておきましょう。山で遭難しないためには山の怖さを知っておく必要があるということです。
① 期待するパフォーマンスのレベル(Should)の定義の問題
モノの場合と違って、ヒトの場合はShouldの設定が当たり前になっていません。考えられる理由としては、日本企業が長きにわたって長期雇用制度を採用していたので、その都度Shouldを厳密に設定する必要性が少なかったという事情が挙げられます。また、単純な機能しか発揮しないモノと違って、臨機応変の対応ができるヒトのShouldを明確に設定するのが難しいという事情もあります。
Shouldが規定されていなければ、問題を設定することはできません。問題が設定できなければ、問題解決もありません。もちろん上司自身は自分がイメージするShouldを持っています。しかし、あくまでもイメージに留まっているので、部下には伝わりません。その結果、いろいろなトラブルが発生することになります。
- 期待されるレベルを理解していない部下は、自分にギャップがあるという認識がない
- 目指すべきものがわからないので、部下はそれに向けた努力をしない
- 自分に対する評価は周囲の空気である程度察知できるが、空気を読めない部下は自分が低い評価を受けていることがわからない
- 上司は低評価の部下がなぜ頑張ろうとしないのかが理解できない
- Shouldが社内で共有されないので、上司の好みに合わないと会社にとって有為な人材でも評価を得られない
このような状況に陥ったら、問題解決は容易ではありません。
② ヒトに関する情報の問題
モノと違ってヒトについては定性的情報が重きをなします。ところが、定性的情報を自動的に集めることはできません。また、定性的情報については解釈の余地があるので、何が正しい情報なのかを決定しにくいという悩ましさがあります。さらに、「その情報はおかしい」とモノが文句を言うことはありませんが、ヒトの定性的情報については本人の言い分も聞く必要があります。
正しい情報をモレなく活用するのが科学的アプローチの大前提ですが、この第1規則と第4規則を守ることはヒトに関しては容易ではないのです。
③ 直感でわかるという思いこみの問題
機械は脅してもすかしても言うことを聞いてくれません。仕方がないので、客観的なデータを収集し、それを分析して対策を考えざるを得ません。ところが、ヒトに関しては、相手も同じ人間です。科学的な検証は一切されていないのに「同じ人間として相手の気持ちはよくわかる」といったフレーズが無批判に受け入れられます。
こうして、ヒトのことはデータに頼らなくても直感でわかるという思い込みがまかり通ります。ヒトの情報が収集しにくいということも直感に頼る傾向を後押しします。直感による判断を仮説として採用することには問題がありませんが、検証をしなければ「恣意的な判断にすぎない」という批判に耐えることができません。
ヒトの問題解決についてはさらに悩ましい問題があります。理性を使った科学的アプローチを提唱したデカルトに対して、同じく17世紀のフランスの哲学者であるパスカル[2]は徹底的に批判を加えています。「心にはわかるが、理性ではわからないことがある。理性だけで真理を捉えることはできない」というのがその主張です。
モノと違って心を持つヒトについてはデカルト的なアプローチが万能とは言い切れません。そのため直感によるアプローチにも一理あることになります。しかしながら、説明責任を求められるのが今の時代です。説明責任を果たすためには、科学的アプローチを活用せざるを得ないのがわれわれの厳しい現実と言えます。
5. ヒトに関する問題解決はどのようにして行えばよいか?
科学的なアプローチによってヒトの問題を解決する場合は、次のようなプロセスが考えられます。
Step 1 Should(期待するパフォーマンスのレベル)の定義
問題とはShould(期待)とActual(現実)のギャップなので、期待するパフォーマンスのレベルであるShouldを明確にしておくことが問題解決のための大前提になります。そこにおいてはShouldの妥当性が問われます。上司の願望を反映しただけのShouldでは現実に対して何の役にも立ちません。
Shouldは2つの要素に分解されます。それはMustとWantです。Mustは必須条件のリストで、これをクリアしなければ期待するパフォーマンスのレベルには到達しない(あるいは、その資格がない)という項目です。Wantは希望条件のリストで、こういうタスクがこなせると期待するレベルへの到達が容易になるという項目です。
成文化した定義がなくても、現実的にはポジションごとにShouldのイメージが職場で共有化されていると思います。したがって、そのようなイメージを手掛かりにして、期待するパフォーマンスのレベルをMustとWantで整理するとよいでしょう。ただし、それは一人前になった状態でのShouldなので、新たに配置された人に対しては、着任してから 一人前になるまでのマイルストーンごとにShouldを設定する必要があります。
これに関連して、GEの有名な「100日プラン」を紹介します。GEはM&Aを行った場合、Day1からDay100までの間、日々何をしなければならないか(Should)を明確に設定しています。そして100日後には買収した会社のDNAをGEの色に染め抜くことを目指しています。会社を丸ごと1日でも早くGEの戦力にしたいからです。直接的にはヒトの問題ではありませんが、Shouldを活用した部下の戦力化というテーマにとって参考になると思います。
Step 2 現状分析
問題解決は、問題を設定するところからスタートします。ヒトの問題設定は、「A君は期待外れだ」というような上司の直感が引き金になることが多いと思います。これはあくまでも感覚なので、科学的アプローチにバトンタッチする必要があります。
科学的アプローチを採用しないと、次のような乱暴なやり取りが行われる危険があります。
上司 「A君はダメだ」
同僚 「なぜですか?」
上司 「能力が足りない。だから交代させよう」
上司の見解は漠然としていて、A君の何がダメなのか、なぜダメと断言できるのかということがまったくわかりません。そのため、短絡的な結論しか導くことができません。適切な問題の設定が問題解決のための前提となるので、先ずはA君を取り巻く状況をできるだけ正確に捉える必要があります。
科学的アプローチで現状を把握するためには、対象をモレなくダブリなく把握する必要があります(デカルトの第4規則)。それによって問題がどこにあるかを探るのです。現状をモレなく把握するためには、次の4つの次元で情報を収集します。それによってヒトを取り巻く情報を空間的にも時間的にもカバーすることができるからです。
■What
・A君の問題となっている言動(ShouldとActualのギャップ)は何か?
■Where
・問題となっている言動はどこで観察されたのか?
■When
・それはいつ初めて観察されたのか?
・それ以来その問題はどのようなタイミングで観察されたのか?
■How (How serious)
・その問題の重大さ、程度はどのようなレベルなのか?
これ に対する回答はA君についての否定的情報になるはずです。そうすると、この問いに答えるだけでは全体をモレなくという第4規則を守れないことになります。なぜならば、あらゆる点で期待に沿わないというヒトはいないからです。うまく行っていないこともあれば、うまく行っていることもあるというのがヒトの真実です。
さらに、人間には自分の好みに合った情報しか見ないというバイアスがあります。一旦A君を否定的に見てしまうと、否定的な情報だけが印象に残って、肯定的な情報を無視してしまう危険性があります。
そこで、この問いに対する回答を観察されたこと(IS)と位置付けて、次に、観察されていないこと(IS NOT)を挙げていきます。ISはbe動詞のisのことで、IS NOTはその否定形です。言い換えればISとIS NOTは、「該当すること」と「該当しないこと」になるので、これによってA君の状況をモレなく拾うことができます。このようなアプローチを採用することで、問題となる状況を把握します。例えば、次のような具合です。
| IS | IS NOT | ||
| What | 何が問題なのか? | A君は指示されたことしかやらない | 同僚のBさんは自発的に行動する |
| Where | どこで観察されるか? | 営業現場 | 営業現場以外。飲み会の幹事役などは買って出る |
| When | 初めて観察されたのは? それ以降は? | 6月頃 継続している | 以前は気付かなかった |
| How | 問題の程度は? | 新規の売上が増えていない | 既存客の売上は維持している |
What、Where、When、HowのISとIS NOTを押さえることで、初めてA君の状況が見えてきます。上司の直感で「A君はダメだ」と決めつける場合と比べて、状況認識に広がりと深さが出てくることがわかると思います。
情報の品質という観点からもこのようなシステマティックなアプローチは威力を発揮します。ヒトに関する良質な情報は収集が難しいので、怪しげな情報が横行する危険性が常にあります。ところが、目についた否定的なIS情報だけでなくて、IS NOTという対照情報も探すとなると、自ずと情報がスクリーニングされることになります。
比較に耐える情報を探さなければならないので、直接情報(自分が直接見た)なのか、間接情報(他人が直接見たことを確認した)なのか、噂(誰が見たかわからない)や臆見(根拠の薄弱な情報に基づいた主観的意見)なのか、ということが気になるからです。こうして、正しいものだけ受け入れる(=Factベース)というデカルトの第1規則(明証性)が担保されるのです。
Step 3 問題の特定
状況分析のISとIS NOTの比較をすることで問題の特定をします。そのためには、観察されたことと観察されていないことの間で明確に区別できる点に注目します。
A君のケースで言うと、指示されたことしかやらないという積極性の欠如が問題視されています。ところが、同じような立場のBさんにはそのような問題が見られません。そのため、A君の受動的な姿勢には問題があるという仮説が成り立ちます。仮にA君以外の人も積極性が欠如していれば、それはA君の問題ではなくなって、職場全体の問題になるはずです。
一方で、A君には飲み会の幹事を買って出るという積極性も見られます。すべての仕事に対して積極性が欠如しているわけではないようです。積極性の欠如といっても問題はそれほど単純ではないことがわかります。
また、A君は新規顧客の開拓に問題を抱えていますが、既存客の売上は維持しています。新規顧客の売上は増やしているけれども既存客の売上を減らしている担当者がいるとしたら、A君に対する見方も変わるかもしれません。
「あいつはヤル気がない」という一言で片づける直感的なアプローチと比べると、科学的アプローチのほうが状況の全体像を多面的に見ていることがわかると思います。それによって判断の公平性が守られるのです。
Step 4 原因の究明
問題となるISとIS NOTのデータを比較することで明らかになった問題点に注目して、問題の原因を究明します。そのためには、ISとIS NOTを明確に区別できる点をもたらした変化に注目します。なんらかの変化が引き金となって問題が生じた可能性があるからです。
ヒトの言動については、どんなに頑張ってもモノのように客観的なデータが豊富に手に入ることはありません。そのため、原因の究明には「過去に似たような問題を見たことはないか」という基本戦略の活用も有効です。経験を積んだビジネスパーソンであれば、自分が若手社員だった頃に似たような状況に追い込まれたことがあるはずです。そこから考えられる原因のヒントを見つけるのです。もちろん先輩、同僚、専門家の意見を求めることも有効です。
問題の原因となるような変化が見当たらない場合、あるいは、配属された当初から問題だった場合は、そもそも本人の現在の実力でShouldが実現できるかというリアリティチェックが必要になります。この場合、問題はA君よりもA君をアサインした上司のほうにあることになります。
Step 5 対策の立案
原因が特定できたら、問題を解決するための対策を講じます。どうしたら期待されるパフォーマンスのレベルの仕事ができるようになるかということです。具体的な対策は実際の仕事に応じて千差万別ですが、ヒトの問題に固有の解決策としては次の2つを挙げることができます。
- 原因となる衛生要因[3]を取り除く
- 足りない能力に対してトレーニングをする
1つ目は、本人以外の要因です。社会的動物である人間にとって職場環境は大きな影響があります。人間関係、偏見、差別、ワークライフバランスといったことが問題の原因となることがあります。このような衛生要因を取り除くことで問題の解決を図ります。
もう1つは本人の問題です。Shouldに到達する実力がなければ問題を解決できません。そのため、能力向上のためのトレーニングを実施します。幸いなことに、機械と違ってヒトの能力は飛躍的な成長を期待することができます。具体的なトレーニングの内容は業務によって変わりますが、上司が部下に対して適切なフィードバックを行うことが対策の基本となります(部下をヤル気にする最強のツール「フィードバック」参照)。問題解決を通して部下の実力を伸ばすのがリーダーに期待される役割です。
科学的アプローチのもうひとつのメリット
科学的アプローチを採用すると、ヒトの問題についての記録を残すことができます。これが日本のビジネスにおいて重要な意味を持ちます。人材の流動性の高いアメリカ企業は、常に雇用に関する訴訟リスクにさらされています。アメリカだから簡単に首を切れるというのはまったくの誤解です。筆者が日本企業からアメリカ企業に転職して最も驚いたのは、ヒトの扱いについてのアメリカ企業の丁寧さです。確かにアメリカ企業ですからヒトの整理を実施しましたが、一人の人に会社を辞めてもらうためには半年にわたって詳細に記録を残すことが求められました。不当解雇で訴えられるリスクに備えるためです。日本においても人材の流動性は高くなるはずです。訴訟の話は別にしても、企業として説明責任を果たすためにも、記録を残すことが不可欠となります。
6. まとめ
モノやカネの問題を解決するときに科学的アプローチに基づいた問題解決の技法が多用されていますが、ヒトの問題に対しても科学的アプローチは有効です。ヒトの問題に対する科学的アプローチのプロセスは次の通りです。
- 期待するパフォーマンスを設定する :Shouldを定義する
- 問題を取り巻く状況を分析する :What、Where、When、Howを調査する
- 問題を特定する :ISとIS NOTを比較する
- 原因を解明する :ISとIS NOTの変化に注目する
- 対策を講じる :衛生要因の除去と能力の向上
モノやカネと違って、ヒトの問題は情報が取りにくいという難しさがあります。さらに、ヒトには心という他にはない要素が絡んできます。そのため直感的なアプローチで問題解決が図られることがあります。直感を否定する必要はありません。それを手掛かりにして、科学的アプローチを使いこなすというのが望ましいやり方と言えます。
ヒトの問題は簡単ではありません。解決するための正解も決まっていません。それでもリーダーは判断をしなければなりません。そして、その判断の影響はお金で解決できる範囲を超えます。商売の問題で判断ミスをしても、お金を損するだけです。次の商売で取り返せば問題は解決します。これに対して、ヒトの問題における判断ミスは相手の人生にネガティブな影響を与える危険性があります。
これはあくまでも筆者の経験ですが、満足のいくビジネスライフを送った人からは「自分は幸運だった」というフレーズをよく聞きます。これに対して、納得のいかないビジネスライフを送った人からは不当評価に対する恨み節を聞かされます。ヒトに対する正しい評価は神様にしかできないので、評価が不当だったかどうかは問題ではありません。納得感のある評価がなかったことが問題だったと言えます。
リーダーに求められるのは、ヒトの問題解決において透明で公平な判断とそれによる納得感のある評価をすることです。だからこそ、科学的アプローチに基づいた問題解決のスキルを磨くことが人の上に立つリーダーにとって重要なのです。
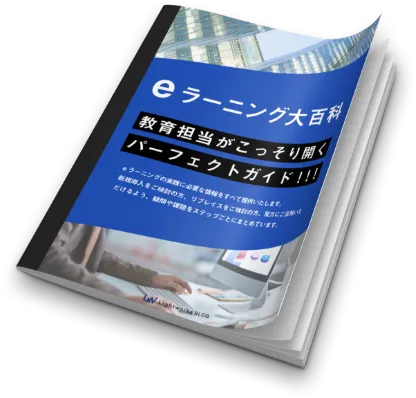
社員教育や人材開発を目的として、
・eラーニングを導入したいが、どう選んだらよいか分からない
・導入したeラーニングを上手く活用できていない
といった悩みを抱えていませんか?
本書は、弊社が20年で1,500社の教育課題に取り組み、
・eラーニングの運用を成功させる方法
・簡単に魅力的な教材を作る方法
・失敗しないベンダーの選び方
など、eラーニングを成功させるための具体的な方法や知識を
全70ページに渡って詳細に解説しているものです。
ぜひ、貴社の人材育成のためにご活用ください。
プライバシーポリシーをご確認いただき「個人情報の取り扱いについて」へご同意の上、「eBookをダウンロード」ボタンを押してください。
[1] デカルトの最も有名なフレーズが「我思う、ゆえに我あり」です。x軸、y軸の座標の発明者でもあります。
[2] 最も有名なフレーズが「人間は考える葦である」です。天気予報で聞くヘクトパスカルのパスカルです。
[3]職場環境において不満足要因となるものを衛生要因と呼びます。
<参考文献>
・Charles H. Kepner & Benjamin B. Tregoe (2013) ”The New Rational Manager” Princeton Press.
・René Descartes, Edition établie par Geneviève Rodis-Lewis(1992), Discours de la méthode, GF-Flammarion.
・ダイヤモンドハーバードビジネス編集部編(1999)「事業ポートフォリオ再構築の技法」ダイヤモンド社.
・デカルト(2011)「方法序説」岩波文庫.
・G・ポリア(2015)「いかにして問題をとくか」丸善出版.
・川喜多二郎(2017)「発想法」中公新書.