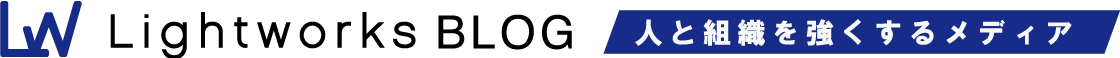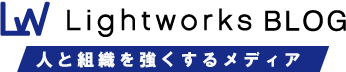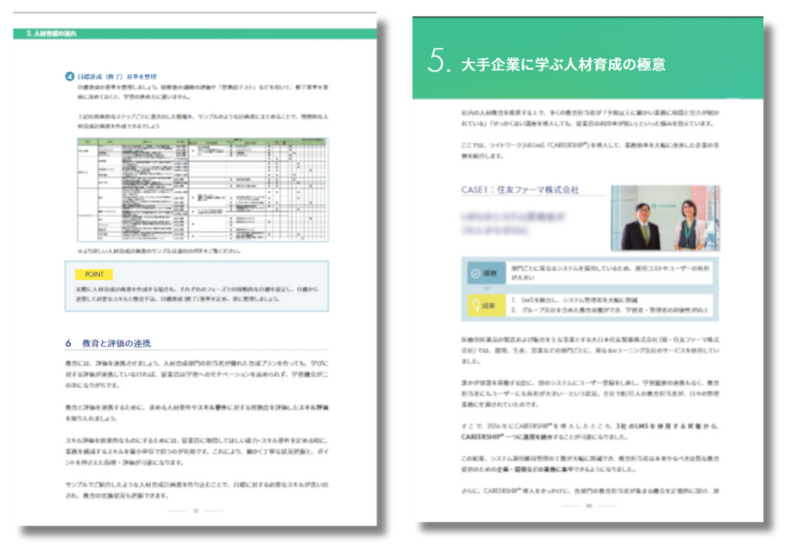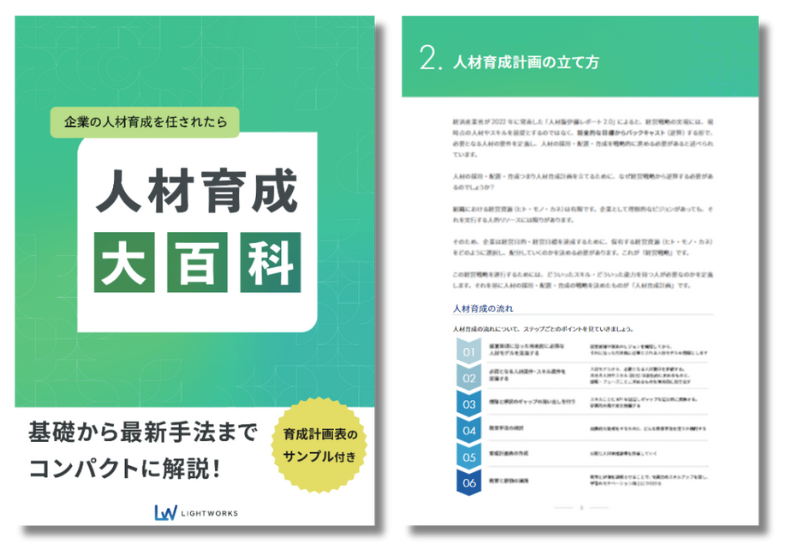「グローカル人材」とは、グローバルに物事を考える視点を持ち、その視点を生かして地域経済や社会に貢献する活動を行う人材のことです。
「グローカル」とは、「グローバル(Global、世界)」と「ローカル(local、地域)」を掛け合わせた造語です。つまり「グローカル人材」は、海外マーケットとの橋渡し役や地域企業の海外進出を担う、世界に通用する能力を持った人材のことを指し、近年注目を浴びています。
このグローカル人材が果たす役割は、地域企業がグローバル市場に展開する、逆にグローバル企業が地域市場に進出する、あるいは地域と地域をつなぐなど多様に解釈することができますが、共通して求められるのは「地球規模で考え、地域で行動する力」です。
本稿では、このグローカル人材への期待が高まっている背景や、グローカル人材が持つ強み、またどうすればこのような人材を育てられるのかなどをご紹介します。
■人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!
「人材育成大百科」の無料ダウンロードはこちらから
目次
1. グローカル人材が注目される背景とは
グローカル人材は、グローバルな視点・経験を生かして地域の発展に貢献する人材のことです。ここでいう「グローバルな視点」とは、外国語スキルだけではなく、異文化への理解力を生かし世界中の人々とコミュニケーションをとる能力を指します。
グローカル人材が注目される理由は、「グローバル人材」との性質の違いにあります。両者はどういった点で異なるのでしょうか?
グローバル人材とは、ご存知の通り、日本人としてのアイデンティティを持ちながら、行動力を生かして海外で活躍できる、いわゆる「世界規模で活躍する」人材を指します。
一方、グローカル人材は、海外でも活躍できるスキルや考え方を持ちつつも、あくまでその地域に貢献する人材です。「世界規模の視点と地域性を組み合わせた性質」を持つ人材といえるでしょう。
ここに、グローカル人材が求められる理由があります。グローバル化の時代の流れは各国の都市部だけでなく、地域社会にまで浸透しました。地方企業はかつての「地産地消」の形態から海外への事業展開へとモデルチェンジすることで、より大きな利益を確保しようと動いています。
その際、どうしても自社を海外マーケットに受け入れられる形で結び付けるための「橋渡し役」が必要となるというわけです。
今や、小規模企業であっても、インターネットを駆使することで海外展開が比較的容易な時代となりました。また、地域企業がグローバルに活躍することで国全体を豊かにするためにも、多くの企業にグローカル人材が必要とされているのです。
人事に関する注目トピックを毎週お届け!⇒メルマガ登録する
eラーニングを成功させるための具体的な方法を詳しく解説⇒「教育担当がこっそり開くパーフェクトガイド eラーニング大百科」をダウンロードする
2. 「グローカル人材」の人材像
それでは、グローカル人材にはどのようなスキルが求められるのでしょうか? 大きく2つ挙げることができます。
- コミュニケーション能力
- ローカライズ能力
それぞれ説明していきます。
2-1. コミュニケーション能力
グローカル人材に求められる最大の役割は、企業を海外マーケットと結び付けるための「橋渡し」です。そのためには、異なる文化・価値観を持つ人とコミュニケーションをとる能力が必須といえます。
外国語の会話スキルや相手の国の文化・礼儀作法といったものに関しては、現地に行ってから慣れるのではなく、事前にしっかりと勉強しておく必要があるでしょう。
2-2. ローカライズ能力
何より重要なのが、異なる価値観を理解し現地の人々に受け入れられるビジネスを展開する姿勢です。自国で培ったノウハウが絶対のものであると思い込まずに、その地域の人々の好みを理解しようとすることが、企業のグローカル化には必要となります。
例えば、マクドナルドの営業戦略は、このローカライズ能力がポイントとなっているといえるでしょう。マクドナルドの商品の中には、販売する地域に合わせて味を独自に調整しているものがあります。日本店舗での「てりやきマックバーガー」は、分かりやすい例です。
このように、他国の企業が海外で成功するためにはローカライズ能力を持つ人材が重要な役割を果たすのです。
3. グローカル人材の育て方・見極め方
こうしたグローカル人材にはどうしたら出会えるのでしょうか? 京都のNPO法人グローカル人材開発センターの取り組みから、グローカル人材の育て方や見極め方について考えてみましょう。
同センターでは、京都府の経済団体・大学などと共同でグローカル人材の育成を目的としてさまざまなプロジェクトに取り組んでいます。取り組みの内容は大きく分けて次の3つがあります。
(1)人材育成プログラム
「自発的な学びの土壌づくり」を目的に、研修プログラムの企画・開発・提供をしています。オリジナル型、オーダーメイド型の2種類があり、課題やニーズに合わせて選ぶことができます
(2)採用力支援プログラム
学生と企業との連携プロジェクトをプロデュースし、企業と学生の新たな「出会いのカタチ」を提供しています。また、外国人材の採用に向けて、外国人留学生の採用支援や、相互理解を深めるための異文化協働研修の提供なども行っています。
(3)教育機関向け支援
課題解決型の教育科目を大学に導入する支援をしています。プロジェクトチームとして課題に取り組む経験を積ませることで、社会人生活において大学で学んだことを生かす力を身に付けさせることが目的です。
グローカル人材として活躍するには実地体験が重要です。海外留学や海外研修で異文化を体験する過程を経て、グローバルな視野・視点を獲得した人は、グローカルな人材として成長していく可能性があります。
ただし、海外に行けば無条件にグローバルな視野・視点が形成されるわけではないため、異文化を理解し積極的に学ぼうとする姿勢が欠かせません。
このように、現地での体験と積極的に学ぶ姿勢、2つの要素を備えていることがグローカル人材として活躍できるかどうかのポイントになるでしょう。
4. まとめ
グローカル人材とは、グローバルな視点や経験を生かして地域社会・地域経済に貢献できる人材です。グローカル人材として活躍するには異文化に対するコミュニケーション能力や、地域の人々の側に立ったローカライズ能力が欠かせません。
このような能力を身に付け、グローカル人材として育つには、海外での学習経験と積極的に学ぶ姿勢が必要だということができます。
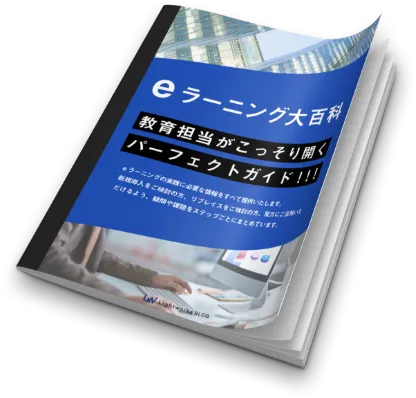
社員教育や人材開発を目的として、
・eラーニングを導入したいが、どう選んだらよいか分からない
・導入したeラーニングを上手く活用できていない
といった悩みを抱えていませんか?
本書は、弊社が20年で1,500社の教育課題に取り組み、
・eラーニングの運用を成功させる方法
・簡単に魅力的な教材を作る方法
・失敗しないベンダーの選び方
など、eラーニングを成功させるための具体的な方法や知識を
全70ページに渡って詳細に解説しているものです。
ぜひ、貴社の人材育成のためにご活用ください。
プライバシーポリシーをご確認いただき「個人情報の取り扱いについて」へご同意の上、「eBookをダウンロード」ボタンを押してください。
(参考)
https://jinjibu.jp/keyword/detl/800/
http://glocalcenter.jp/
https://bizhint.jp/keyword/78897
https://bizhint.jp/keyword/97269
https://paraft.jp/r000017002541