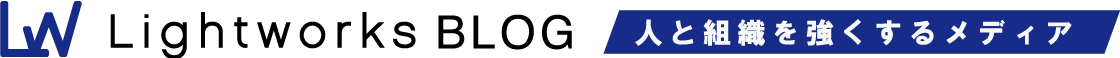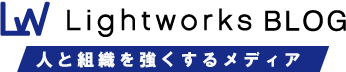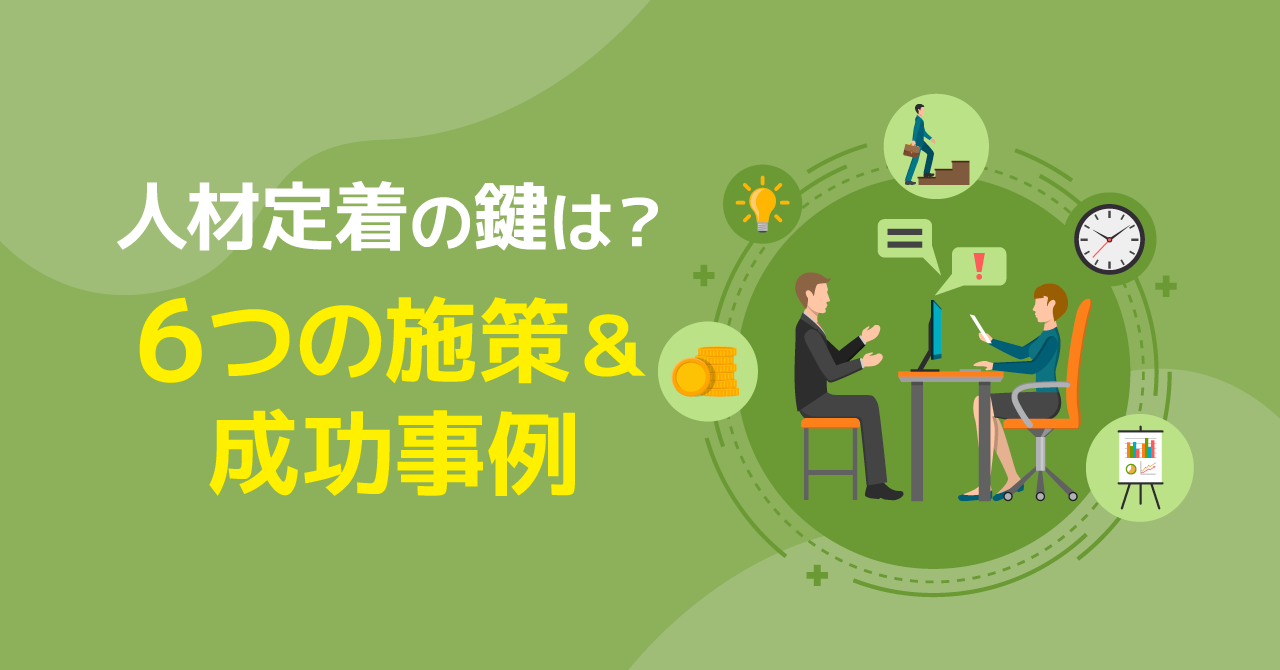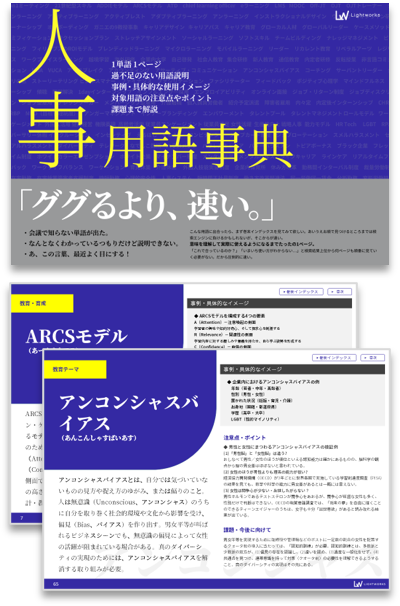リテンションマネジメントとは、従業員の離職防止のために行う人事施策全体を指します。人材流出は多くの企業が課題としており、従業員が長期にわたって働き、活躍できる環境づくりの必要性が増しています。
(一社)日本経営協会の「人材白書2023」によると、人材開発において企業や官公庁が直面している課題のうち、「若手社(職)員の定着率の低さ(27.8%)」「コア人材の流出(21.0%)」の比率が、コロナ禍以前に比べて大きく増えていることがわかりました[1]。
近年、働く人の価値観や生活スタイルなどが多様化し、若い世代を中心に、より自分に合った働き方を求める傾向が高まっています。多様な価値観に応えることは、従業員のエンゲージメント向上、ひいてはリテンション(定着)につながります。
この記事では、従業員の定着率向上を目指す人事施策である、リテンションマネジメントについて、基礎知識から具体的な施策、注意点、導入のステップ、成功事例まで網羅的に解説します。
「リテンションマネジメント」のほか、「ARCSモデル」や「エンプロイアビリティ」など、近年話題の人事系キーワードについて詳しく知りたい場合は、163の用語を解説している「人事用語事典」(無料)をご利用ください。
目次
リテンションマネジメントとは?
リテンションマネジメントとは、好業績を上げる従業員、または将来好業績を上げるであろう従業員の流出を防ぎ、長期間自社で力を発揮してもらうために行う人事施策全体のことを指します。
従業員の定着を目指す施策は、単独の取り組みがあるわけではありません。従業員の満足度やエンゲージメント、モチベーション向上などを目指すさまざまな施策を同時に実施し、それぞれの目標を達成することで従業員の定着を図ります。
なぜ今、リテンションマネジメントが重要なのか?
なぜ今リテンションマネジメントが重要かというと、人材獲得だけでなく人材流出が多くの企業にとって課題となっているからです。
日本は少子高齢化により生産年齢人口が減少しています。加えて、20~30代の若い世代を中心に、給与アップやキャリアアップなど、新たなチャンスの獲得を求めた転職が一般的になりつつあり、優秀な人材を巡る企業間の獲得競争が起きています。
このようなことから、組織として持続的な成長につなげるために、従業員の定着率向上を図り、個々の能力を最大限に引き出すリテンションマネジメントが重要視されているのです。
リテンションマネジメントで従業員の定着と能力開発が促進されれば、従業員にとってモチベーションやエンゲージメントの向上につながります。結果として、従業員個人のキャリアプランと組織の目標達成、双方の実現が期待できるでしょう。
リテンションマネジメントがもたらすメリット
リテンションマネジメントは、コスト削減、生産性向上、企業の魅力向上、組織の活性化など、さまざまなメリットをもたらす可能性があります。ここでは、4つの主なメリットについて解説します。
コスト削減:採用・教育費用の抑制
リテンションマネジメントによって従業員の定着率が高まると、採用活動や新人教育にかかるコストを削減できます。
従業員の退職によって新たな人員を補填する場合、考えられる費用は以下があります。
- 採用広告の掲載費用
- 採用イベントの開催費用
- 人材紹介会社への手数料
- 面接官の人件費 など
また、採用後は新人研修の開催費用(会場や機材のレンタル費用、講師への謝礼、資料の作成費用など)、OJTのための人件費などがかかることもあるでしょう。
リテンションマネジメントに取り組み、採用活動や新人教育にかかるコストを削減できれば、企業の成長・発展に必要な研究開発や新規事業の立ち上げなどに経営資源を投資しやすくなります。
加えて、人材が定着することで一人一人の適性や個性を把握しやすくなり、長期的な視点で人材育成に取り組める点もメリットです。
生産性向上:経験と知識の蓄積による効率化
従業員の定着率が高まると、企業内に経験や知識を蓄積した人材が増え、企業全体の生産性向上につながります。
長年業務に携わり知識やスキルを培ってきたベテラン従業員は、過去の経験に基づき、問題解決や業務改善の提案を行うことも期待できるでしょう。優秀な人材の持つノウハウやスキルは知的資産となり、企業価値を高め、競争優位性を確立するための重要な要素となります。
さらに、ベテラン従業員がメンターとなり新人を指導することで、新人の早期戦力化も期待できます。
このようなことから、リテンションマネジメントは、短期的なコスト削減だけでなく、持続的な成長を実現できる土台づくりにつながるでしょう。
企業の魅力向上:優秀な人材を引きつけ、定着させる好循環
リテンションマネジメントの成功は、企業の魅力を高め、優秀な人材の獲得と定着を促進する好循環を生み出します。従業員の定着は企業全体の生産性向上と企業成長を促し、より魅力的な雇用環境の創出につながります。その結果、優秀な人材がさらに集まり、定着する好循環が生まれるのです。
組織の活性化:従業員のエンゲージメント向上
リテンションマネジメントによって従業員のエンゲージメントが向上すると、従業員の定着率が高まり、組織全体の活性化につながります。
エンゲージメントの高い従業員は、企業目標への共感や企業に対する愛着などが強く、意欲的に仕事に取り組むため、自発的に行動し、高いパフォーマンスを発揮する傾向にあります。このような従業員が増加すると、組織全体の活力が高まり、革新的なアイデアが生まれやすくなります。
また、従業員同士のコミュニケーションも円滑になり、協力的な関係が築きやすくなるため、生産性向上や、より良いサービス提供にもつながります。結果として、顧客満足度向上や企業成長を促進するでしょう。
リテンションマネジメントの具体的な施策
従業員の定着率を高めるためには、多面的な施策が必要です。ここでは、リテンションマネジメントの具体的な施策を6つのカテゴリ別に解説します。
報酬・評価制度の見直し
従業員が納得感を持って仕事に取り組むためには、適切な評価と報酬が不可欠です。現状の制度が従業員の貢献度や市場価値を適切に反映しているかを見直し、必要に応じて改善しましょう。
公正で透明な評価基準の設定
評価基準を明確化し、従業員に公開することで、評価に対する納得感を高めます。どのような成果や行動が評価されるのかを具体的に示すことが重要です。
市場競争力のある報酬水準の維持
定期的に市場調査を行って他社の報酬水準を把握し、自社の報酬に競争力があるかを判断します。魅力的な報酬水準を維持することができれば、優秀な人材の獲得・定着につながるでしょう。
成果と連動した報酬制度
従業員の成果や貢献度に応じて報酬が変化する仕組みを導入することで、モチベーション向上を図ります。業務目標の達成度合いを適切に評価し、報酬に反映させることが重要です。
長期インセンティブ制度の導入
長期インセンティブ制度を取り入れることで、従業員の企業への貢献意欲を高め、定着を促進する効果が期待できます。なぜなら、従業員が将来の報酬アップを見据え、企業の継続的な業績向上に向けてより意欲的に取り組むようになると考えられるからです。
長期インセンティブ制度には、ストックオプション(StockOption:自社株式を一定の価格で購入する権利を付与)、リストリクテッドストック(RestrictedStock:一定期間の譲渡制限を設けた自社株式の付与)などがあります。
働きがいのある環境づくり
従業員が快適に働ける環境を整備することは、リテンションマネジメントにおいて非常に重要です。
ワークライフバランスの推進
労働時間の適正化、柔軟な働き方(フレックスタイム制、テレワークなど)の導入、有給休暇の取得促進など、従業員が仕事とプライベートを両立しやすい環境を整備します。
労働環境の改善
オフィス環境の整備やハラスメント対策など、従業員が安心して働ける職場環境づくりに取り組みます。
成長機会の提供
従業員の成長意欲に応えるため、多様な成長機会を提供します。
研修制度の充実
階層別研修やスキルアップ研修の実施、eラーニングの導入など、従業員の能力・スキル向上を支援する研修プログラムを整備します。
資格取得支援
業務に必要な資格の取得を奨励し、取得にかかる費用や時間などについて、積極的に支援します。例えば、受験料や学習教材費、レッスン受講料などの補助、学習時間の確保に向けた業務量や勤務シフトの調整、社内勉強会の開催などが挙げられます。
キャリア形成支援
定期的な面談やキャリア相談会を実施し、従業員のキャリアプランを把握し、その実現をサポートします。キャリアプランの実現に必要な業務経験やスキルなどを明示し、獲得を促したり、社内公募制度やジョブローテーションなど、新たな挑戦の機会を提供したりすることが有効です。
メンター制度の導入
メンター制度とは、経験豊富な先輩従業員がメンターとなり、若手従業員の成長をサポートする制度です。双方向の対話を通じて、若手従業員の業務やキャリア、人間関係などの課題や悩みの解決を支援し、成長の促進につなげます。
組織文化・風土改革
従業員が働きやすい組織文化・風土を醸成することは、リテンションマネジメントの基盤となります。
風通しの良い職場環境
上司や部下、同僚がお互い気軽にコミュニケーションを取れる環境づくりを推進します。具体的には、1on1ミーティングの導入、社内SNSやチャットツールの活用、社内イベントの開催などが考えられます。
多様性を尊重する文化
性別、年齢、国籍、文化などの違いを尊重し、協力し合える職場環境を築きます。制度面では、多様性に関する方針の明文化、ハラスメント防止対策強化、合理的配慮の提供、多様な人材の採用促進などが挙げられます。多様なニーズに対応した福利厚生の整備、相談窓口の設置なども有効です。
従業員の意見を尊重する体制
従業員の意見や提案を積極的に取り入れ、改善につなげる仕組みを構築します。従業員満足度調査などを活用して従業員の声を定期的に収集・分析し、体制改善に反映させましょう。
労使コミュニケーションの活性化
経営層と従業員間のコミュニケーションを活性化することで、相互理解を深め、組織の一体感を醸成します。
対話機会の創出
経営陣の考えや自社の現状を従業員に伝え、従業員の意見や要望を経営陣が直接聞く機会を設けましょう。例えば、ざっくばらんに意見を伝い合えるよう、タウンホールミーティングや懇親会、意見交換会などを開催するといった方法が考えられます。
社内コミュニケーションツールの活用
社内報やイントラネット、社内SNSなどを活用し、企業のビジョンや経営状況、人事制度の変更などをタイムリーかつ分かりやすく伝えます。加えて、従業員が自由に意見やアイデアを発信できる場を設けることで、双方向のコミュニケーションを促進します。
社内提案制度の導入
従業員からの提案を積極的に募集し、優れた提案を採用する制度を導入します。これにより、従業員の主体性を高め、業務改善や新サービス創出につながります。
さらに、従業員が「自分たちの提案を聞き、受け入れを検討してくれる」と感じることで、従業員エンゲージメントの向上も期待できるでしょう。
福利厚生の充実
従業員のニーズを踏まえ、魅力的かつ充実した福利厚生を提供することで、従業員の満足度を高め、定着促進につながります。
育児・介護支援制度
育児休業、介護休業、短時間勤務制度など、仕事と家庭の両立を支援する制度を整備します。
健康増進施策
健康診断、インフルエンザ予防接種、スポーツジムの利用など、従業員の健康をサポートする制度を導入します。
社内イベントの実施
懇親会、社員旅行、サークル活動など、従業員同士の交流を深める機会を設けます。
住宅手当、社員寮の提供
従業員の住居にかかる費用負担を軽減する制度を導入することで、経済的な支援を行います。
従業員のニーズを把握した上で、これらの施策を組み合わせて実施すると、相乗効果を発揮し、より効果的なリテンションマネジメントを実現できるでしょう。
リテンションに悪い影響を与える施策
従業員の定着を促進するためには、労働時間や報酬、福利厚生、自由な働き方などに関する複数の施策を講じることが重要です。しかし、中にはリテンションに悪影響を与える施策も存在します。
青山学院大学の山本寛教授による論文[2]では、リテンションに悪い影響を与える施策として変動給、電子的監視システムなどが挙げられています。これらの施策を実施せざるを得ない場合は、リテンションに良い影響を与える施策とセットで行うことが有効といえるでしょう。
一方、リテンションに良い影響を与える施策や要素には、現実的職務予告(採用過程において入社希望者に業務や組織ついての情報をネガティブな面も含め開示すること)、給与が高いこと、労働時間が短いこと、従業員持ち株制度を挙げています。
また、労働時間や報酬、職場環境の改革など複数の施策を実施する際は、施策目的が首尾一貫していることが重要です。例えば、成果主義による報酬決定と年功序列制度のように親和性の低い施策を同時に行うと施策間の相乗効果が期待できず、結果としてリテンションの効果も薄れてしまうでしょう。
さらに、施策実施後はリテンションの効果を高める要因、阻害する要因の調査・特定も求められます。施策効果を左右する要因としては、組織文化や風土、上司のリーダーシップなどが考えられます。
リテンションマネジメント導入のステップ
ここでは、リテンションマネジメント導入の3つのステップを解説します。
現状分析:課題とニーズの明確化
リテンションマネジメントを成功させるためには、現状分析を行い、自社の課題とニーズを明確にすることが重要です。
まず、従業員アンケートやヒアリング調査などを通じて、従業員の満足度やエンゲージメントレベル、離職理由などを把握します。次に、部門別・職種別・勤続年数別などの属性ごとに分析を行い、課題を具体的に特定します。
例えば、若手社員の早期離職率が高い場合は、労働時間や休暇の取りやすさといった労働条件の不満やキャリアパスへの不安、成長機会の不足などの要因が考えられます。また、管理職層のエンゲージメントが低い場合は、ワークライフバランスの実現が困難、評価制度の不満などが課題として挙げられるでしょう。
分析結果に基づいて、自社の課題とニーズを明確化し、効果的なリテンションマネジメント施策を検討していく必要があります。
計画策定:具体的な目標設定と施策の選定
リテンションマネジメントを成功させるには、具体的な目標設定と、達成のための適切な施策選定が重要です。
まず、現状分析で明らかになった課題やニーズを踏まえ、目標を設定します。目標は、従業員定着率の向上や、特定の職種における離職率の抑制など、具体的かつ測定可能なものにする必要があります。
次に、設定した目標を達成するために、適切な施策を選定します。施策は、企業の規模や業種、従業員の属性や課題などによって異なります。
例えば、従業員満足度調査の結果から、労働時間の長さやワークライフバランスへの不満が課題として明らかになった場合は、柔軟な働き方ができる制度の導入や、有休休暇取得の推奨といった施策が考えられるでしょう。
また、優秀な人材の流出を防ぐためには、キャリアパスの明確化や、スキルアップ研修などキャリア形成を支援する制度の充実といった施策が有効です。
重要なポイントは、自社の課題やニーズに適した施策を組み合わせて実施することです。施策の効果を最大化できるよう、割り当てられる予算や人員なども考慮しながら計画を立てましょう。
実施と効果測定:PDCAサイクルによる継続的な改善
リテンションマネジメントにおいては、PDCAサイクルを回し続けることが重要です。計画に基づいて施策を実行した後は、その効果を測定し、改善策を検討する必要があります。
施策の効果を測定する際には、従業員満足度調査・エンゲージメント調査の結果や離職率・定着率などを指標に用います。目標に対する達成度合いを適切に評価し、課題や改善点を見つけ出しましょう。
そして、効果測定の結果に基づいて計画の見直しや改善を行い、次の施策に生かしていくことで、より効果的なリテンションマネジメントの実現を目指します。
効果測定の結果は、従業員へのフィードバックや経営層への報告にも活用し、組織全体でリテンションマネジメントの重要性を共有するようにしましょう。
成功事例から学ぶリテンションマネジント
ここでは、リテンションマネジメントの具体的な施策例として、株式会社エー・ディー・ワークス、三井化学株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社の3社の事例を紹介します。
株式会社エー・ディー・ワークス
資産関連サービス事業を展開する株式会社エー・ディー・ワークスは、金銭的報酬を中心とした施策によるリテンションマネジメントを行っています。具体的な取り組みは以下の通りです。
市場報酬水準を意識した報酬設定・改定
市場報酬水準を常に把握し、それを上回る水準で採用時の報酬設定、既存従業員の報酬改定をしています。競争力の高い報酬水準により、優秀な人材の採用・確保につながっています。
キャッシュ型長期業績連動報酬(LTI)
業績目標が達成すれば、個人業績に関係なく向こう3年間固定額を支給しています。将来の報酬アップが確約されるため、従業員のモチベーション維持や定着につながっています。
2017年新卒入社者を対象に譲渡制限付き株式を付与
36万円相当の自社株式(譲渡制限期間1年)を新卒入社者に支給しています。企業成長に応じて将来の資産が拡大するため企業価値向上への意欲アップにつながる他、顧客層である個人富裕層視点を経験する機会となっています。
これらの取り組みの結果、2010年には44人だった従業員が2018年9月には155人と3倍以上に増加し、大手企業の優秀な人材も獲得することができています。また、自社の業績や株価に応じた中長期的な報酬によって、従業員の安心感や信頼感を醸成でき、従業員側も自社の状況を自然に意識するようになりました。
このように、同社では金銭的報酬を中心とした施策により採用力の強化と従業員の定着促進を図ることができました。
しかし、金銭的報酬だけでは従業員の自律的な成長につながりにくいことから、内的報酬(仕事に取り組むことそのもので得られる成長実感や満足感、やりがいなど)の提供についても強化の必要性を認識しています。
今後は、従業員への満足度調査や幸福度調査を基に、従業員全体が自由度高く働けるなど、内的報酬を実感できる仕組みづくりに取り組んでいくようです。
三井化学株式会社
製造業の三井化学株式会社は人材に関する主要課題を特定し、中でも「人材の獲得・育成・リテンション」「従業員エンゲージメント向上」などを優先課題として掲げています。主な取り組みは以下の通りです。
グローバル従業員エンゲージメント調査
従業員のコンディションを定期的に調査し、モニタリングと改善施策を実施しています。調査結果で特定された課題には、グループ全社の取り組みに加え、各組織での改善施策も講じ、きめ細かくタイムリーに対応しています。代表的な例は、交流イベント・勉強会の実施、表彰制度の活用、1on1面談などです。
競争力のある報酬水準の設定
各国・地域の労働市場において、競争力のある報酬水準になるよう設定しています。報酬水準は行政機関による各種賃金統計などを参考に定期的に見直し、ベースアップや報酬制度の改定を行っています。
公平公正かつ透明性の高い評価制度
業績成果を適切に反映する公平公正な評価制度を構築し、給与・賞与・評価・昇給などの体系を社内に公開しています。従業員が設定した職務目標に関して、年に1回上司が目標設定面談を行う他、業績評価のフィードバック面談も実施しています。
また、フィードバック面談の実施率やフィードバックの納得度などを三井化学労働組合が調査し、評価制度の適正運営に努めています。
働きやすい職場環境の整備
従業員が多様な働き方で活躍できるよう、テレワークやフレックスタイム制、社内公募制度の導入、副業の許可、服装の自由化などを行っています。
ワークライフバランスを促進する制度の導入
ワークライフバランスに配慮し、以下のような制度・施策を実施しています。
- リフレッシュ休暇(有給)
- 特別休暇(有給)
- 社会活動休暇(有給)
- 育児休業(最長4年、最初の5日間有給)
- 会社託児所の設置
- 看護休暇(有給)
- 介護休業(対象親族1人につき1年まで)
- 介護休暇(有給、年間20日まで)
同社では、今後もさまざまな施策を通して従業員一人一人の能力を最大限引き出し、自主・自立・協働を体現する「挑戦し続ける組織」を目指して変革を続けるとしています。
三菱UFJ信託銀行株式会社
金融業の三菱UFJ信託銀行株式会社は、サービスの多様化・複雑化に伴って高度な専門性を持つ多様な人材を必要としつつも、特に一部領域で採用やリテンションが困難となっていました。そのため、従前のメンバーシップ型人事に加えて、ジョブ型人事も導入しています。
同社はジョブ型人事の導入に際し、2020年4月に全社の人事制度を職務給重視の評価体系にシフトしました。その後、ジョブ型人事の対象となる範囲を段階的に拡充、2021年4月からはファンドマネージャー、2023年4月からは定年後再雇用者を対象とし、2024年4月からは個別業務領域ごとに設定できるようにしました。
具体的な取り組み内容は以下の通りです。
ジョブ型人事
・プロフェッショナルジョブ人事制度
個別業務領域ごとにジョブ型人事の適用を設定できる制度です。対象となる従業員は企業側が指名し、本人の同意をもって決定します。報酬は、各ジョブの市場価値に応じて社内の「専門性認定会議」において決定されます。
・シニアジョブコース
定年後の再雇用者向けに導入したジョブ型人事制度です。「高度な専門性等を兼ね備えた社員」「組織運営や実務推進において欠かせない社員」の2つの区分でそれぞれ選定します。選定された従業員は職務給となり、給与は年50万~100万円ほどの増加が見込まれます。
・ジュニアフェロー制度
学術的な研究・基礎調査を担う職位「フェロー」に就く人材を計画的に育成する制度です。「ジュニアフェロー」(若手のフェロー予備群)を任命し、フェローになるために必要な調査・研究費として年間100万円を支給しています。
ジョブ型人事の対象従業員は、原則として異動がなく、成果が出せなかった場合は賃金の大幅な低下もあり得ます。
メンバーシップ型人事
・若手従業員への積極的な支援
若年層の採用が困難になっていることから、初任給や入社5年目までの賃金引き上げ、若手従業員の早期登用などを行っています。
・転任手当の創設
1回の転勤につき50万円、転勤から戻ってくる際に改めて50万円を支給しています。
ジョブ型人事・メンバーシップ型人事の選択は、原則入社後に業務領域と従業員本人の希望によって決定しています。ジョブ型人事を導入した結果、高度な専門性を持つ人材の採用・リテンションに一定の効果が認められ、人材の多様化促進にもつながりました。
今後は従業員の要望を踏まえ、ジョブ型人事の対象範囲を広げていく方針です。ただし、複数の部署を経験させながら育成する領域や、業務を明確に定義しにくい領域があることから、今後もジョブ型人事・メンバーシップ型人事の併用を続けていきます。
まとめ
リテンションマネジメントとは、従業員の定着率向上のために行う人事施策全体のことです。多くの企業が人材の獲得・流出を課題とする今、優秀な人材の定着は持続的な企業成長に必要不可欠です。
リテンションマネジメントのメリットとしては、以下が挙げられます。
- 採用・教育のコスト削減
- 経験と知識の蓄積による生産性向上
- 雇用環境が整うことによる企業の魅力向上
- 従業員のエンゲージメント向上による組織活性化
リテンションマネジメントの具体的な施策としては、以下が挙げられます。
- 報酬・評価制度の見直し
- 働きがいのある環境づくり
- 成長機会の提供
- 組織文化・風土改革
- 労使コミュニケーションの活性化
- 福利厚生の充実
施策の中にはリテンションに悪い影響を与えるものもあります。例えば、変動給、電子的監視システムなどです。このような施策を実施せざるを得ない場合、リテンションに良い影響を与える施策とセットで行いましょう。
リテンションに良い影響を与える施策や要素としては、現実的職務予告、給与が高いこと、労働時間が短いこと、従業員持ち株制度などが挙げられます。
リテンションマネジメントを導入する流れは以下の通りです。
- 自社の課題とニーズの明確化
- 現状分析を基にした目標設定、施策選定
- 施策の実施と効果測定
リテンションマネジメントを行う際は、PDCAサイクルを回して継続的に改善することが重要です。
リテンションマネジメントの成功事例として、以下3社を紹介しました。
・株式会社エー・ディー・ワークス
市場報酬水準を意識した報酬設定・改定、キャッシュ型長期業績連動報酬(LTI)、2017年度新卒入社者を対象にした譲渡制限付き株式の付与など
・三井化学株式会社
競争力のある報酬水準の設定、公平公正かつ透明性の高い評価制度、多様な働き方やワークライフバランスを促進する制度など
・三菱UFJ信託銀行株式会社
従来のメンバーシップ型人事に加え、一部領域でジョブ型人事を導入
企業の持続的な成長のためには、人材が定着し、自身の能力を発揮して長期間活躍してくれることが重要です。従業員個人のキャリアプランと組織の目標達成、双方の実現につながるよう、自社に適したリテンションマネジメントを検討してみてはいかがでしょうか。
[1] 一般社団法人日本経営協会「人材白書2023」, 2024年4月3日公表 , (2025年1月20日閲覧)
[2] 山本寛「人手不足に対応する事後の人的資源管理──リテンション・マネジメントの観点から」,『日本労働研究雑誌』,No.673,2016,P20-24,(閲覧日:2024年11月4日)
参考)
経済産業省「企業の戦略的人事機能の強化に関する調査(経営力強化に向けた人材マネジメントに関する提言および先進企業事例)【報告書】」, 2019年3月29日公表,https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/jinzai_management/pdf/20190329_01.pdf (閲覧日:2024年12月25日)
マーサージャパン「企業の戦略的人事機能の強化に関する調査(経営力強化に向けた人材マネジメントに関する提言および先進企業事例)【報告書】」,2019年3月29日公表,https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/jinzai_management/pdf/20190329_01.pdf(閲覧日:2024年1月3日)
経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書~人材版伊藤レポート2.0~実践事例集」,p67-69.https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0_cases.pdf(閲覧日:2024年1月3日)
三井化学株式会社「人材マネジメント」,『Mitui Chemicals』,https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/society/employee/engagement/index.htm(閲覧日:2024年1月3日)
内閣官房,経済産業省,厚生労働省「ジョブ型人事指針」,2024年8月28日公表,p207-208.https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/jobgatajinji.pdf(閲覧日:2024年1月3日)