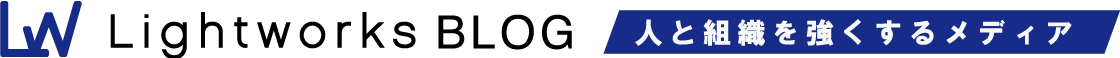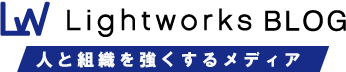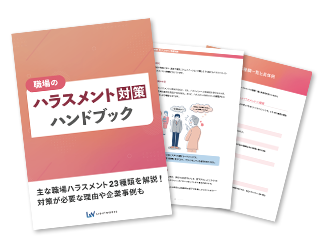さまざまなハラスメントが社会問題となる中、特に顧客からのハラスメント行為「カスハラ(カスタマーハラスメント)」が問題視されています。
2024年10月には、東京都で全国初のカスハラ防止条例が成立しました[1]。厚生労働省も2024年7月にカスハラ対策を企業に義務付ける方針を示す[2]など、社会課題としてカスハラ対策に取り組む動きが強まっています。
この記事では、カスハラとはどのような行為なのか、クレームとの違いや企業が行うべきカスハラ対策について解説します。カスハラ対策の強化を検討している方はぜひご参考にしてください。
\後で読み返しできるハラスメントの解説資料はこちら(無料)/
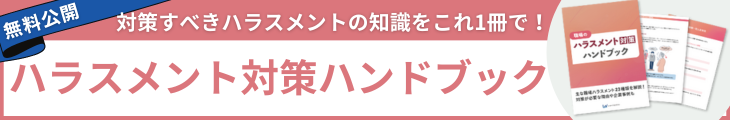
目次
カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?
カスハラとは「カスタマーハラスメント」の略称で、一般的に顧客や取引先からの著しい迷惑行為を指します。
カスハラ(カスタマーハラスメント)の定義
厚生労働省が発行している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、企業の現場において以下のようなものがカスハラに該当するとしています。
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
引用元:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」,2022年2月公表,p7(閲覧日:2024年11月12日)
つまり、顧客や取引先から受けたクレームなどのうち、不当なものや業務を妨害するほど悪質なものがカスハラに当たるということです。
かつて企業は「お客様は神様」という意識で顧客対応を行っていました。しかしカスハラが原因で従業員の心身の不調や離職などを招くケースも多く、企業にはカスハラに対する適切な対処が求められています。
カスハラに該当する行為の例
厚生労働省のカスハラ対策マニュアルでは、以下のような行為がカスハラに該当するとされています。
- 暴行や傷害などの身体的な攻撃
- 脅迫や暴言、中傷などの精神的な攻撃
- 土下座の強要
- 居座りや監禁などの拘束的行為
- 不当な言動(威圧的、差別的、性的)
- 従業員個人への攻撃・要求
また、以下の要求行為は、妥当性によってカスハラに該当する場合があるとされています。
- 商品交換
- 金銭補償
- 謝罪(土下座を除く)
実際のカスハラの事例
厚生労働省のマニュアルには、顧客と接する機会が多い小売、運輸、飲食サービス、宿泊などの業種の企業が実際に受けた具体的なカスハラの事例が挙げられています。以下に一部をご紹介します。
- 頻繁に来店しその度にクレームを入れる
- 大声・暴言で執拗(しつよう)にオペレーターを責める
- 同じ質問を繰り返し、対応のミスが出たところを責める
- SNSやマスコミへの暴露をほのめかした脅し
- 入手困難な商品の過剰要求
- 難癖をつけたキャンセル料の未払い・代金の返金要求
- 特定の従業員へのつきまとい
正当な理由がないにもかかわらず過剰な要求をしたり、対応者の揚げ足を取ったりという事案が多いようです。
タイプ別のカスハラ対策や対応例が学べる! ⇒ ライトワークスのeラーニング「誰もが安心して働ける職場を実現!「カスタマーハラスメント」対策コース」を詳しく見る
企業間のカスハラも存在する
カスハラは顧客からのハラスメント行為というイメージがありますが、企業間でも発生します。例えば、以下のような例です。
- 発注元からの無理難題に対応させられた
- 取引先から誹謗(ひぼう)中傷を受けた
- 取引先担当者から、性的な対応を要求された
こうした不当な要求などがあっても、取引解消を恐れて受け入れてしまうケースは少なくありません。
これまで、優越的な立場を利用して取引先に不当な要求を行う事例は、公正取引委員会などによって規制や是正がされてきました。しかし今後は、同様の事例や、より軽い事例もカスハラと見なされ、ステークホルダーから「コンプライアンスに問題がある」と判断される可能性があります。
産業労働局は2024年7月に「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方」を公表し、取引先と接する際に事業者が行うべき措置について、以下のように記載しています。
⑷ 取引先と接するに当たっての対応
・立場の弱い取引先等に無理な要求をしない、取引先の就業者への言動にも注意を払う
・自社の社員が取引先でカスタマーハラスメント行為を疑われ、事実確認等を求められた場合は協力する 等引用元:産業労働局「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方」,2024年7月公表,p16(閲覧日:2024年11月12日)
従業員には、カスハラを受けた場合の対応を学んでもらうと同時に、取引先に対してカスハラをしないように指導することも重要です。
人事に関する注目トピックを毎週お届け!⇒メルマガ登録する
カスハラ(カスタマーハラスメント)の現状と背景
日本において、カスハラはどのくらい発生しているのでしょうか。また、その背景にはどのような原因があるのでしょうか。本章では、日本のカスハラの現状と背景をひもときます。
日本におけるカスハラの現状
2024年に実施されたカスハラに関する各種調査では、サービス業従事者の約5割、企業の約2割がカスハラを受けた経験があることが分かっています。
サービス業従事者を対象に行われたUAゼンセンのアンケート調査[3]では、直近2年間でカスハラ被害にあった人の割合は46.8%でした。また、東京商工リサーチによる企業向けアンケート調査[4]では、直近1年間で19.1%の企業が「カスハラを受けたことがある」と回答しています。
さらに、2023年に厚生労働省が企業に対して行った調査[5]によると、パワハラやセクハラの相談件数は減少傾向にあるにもかかわらず、カスハラは相談件数が増加傾向にあることが分かっています。
企業のカスハラ対策は十分とは言えない状況
東京商工リサーチの調査では、カスハラを受けたことのある企業のうち、従業員の休職や退職が発生した企業は13.5%でした。カスハラ被害が発生した企業のうち、10社に1社で休職や退職が発生していることになります。
その一方で、カスハラについて特に対策を講じていない企業は7割超となっています。
カスハラの被害が多く発生しているにもかかわらず、企業の対策は十分に行われていない状況といえるのではないでしょうか。
小売業で実際に効果のあった「カスハラ対策」の事例を解説! ⇒ ライトワークスのeラーニング「誰もが安心して働ける職場を実現!「カスタマーハラスメント」対策コース (小売業編)」を詳しく見る
カスハラが発生する背景
カスハラが発生する背景にはさまざまな要因が考えられますが、大きな要因として、以下の二つが挙げられます。
- スマートフォンの普及
- さまざまなハラスメントの表面化
スマートフォンの普及
まず挙げられるのは、スマートフォンの普及です。
消費者はSNSやブログ、口コミサイトなどで気軽に情報を発信できるようになり、クレーム対応中の従業員を撮影した動画や写真などをアップロードする人々が現れました。投稿された動画や写真は、その場にいない人々にも拡散されてしまいます。
スマートフォンの普及によって、消費者の発言力や誤った権利意識が高まり、軽々しく誹謗中傷を行いやすい環境ができてしまったのです。
さまざまなハラスメントの表面化
多様なハラスメントが問題視されるようになったことも影響しているでしょう。
以前から顧客によるハラスメントはありましたが、顧客対応の範囲とされ、公にされることがありませんでした。
しかしセクハラ・パワハラをはじめとした多様なハラスメントが社会的な問題となり、カスハラも世間から注目を浴びるようになったのです。
このように、日本ではスマートフォンの普及やさまざまなハラスメントの表面化により、カスハラが問題となっています。
カスハラ(カスタマーハラスメント)とクレームの境目は?
いざ顧客から苦情を受けた際、カスハラなのかクレームなのか判断に迷うこともあるでしょう。
ここでは、カスハラとクレームの境目をどのように判断するか解説します。
カスハラとクレームの違い
英語のクレーム(Claim)は「要求」「主張」といった意味で訳されます。
日本では「苦情」という意味合いで使われることが多く見受けられます。しかし、商品やサービスの改善要求などポジティブなクレームも存在します。
常識に照らして妥当なクレームには真摯(しんし)に対応すべきでしょう。
一方、カスハラとは、先述の通り顧客からの著しい迷惑行為をいいます。暴言・暴力などのほか、クレームのうち、悪質で妥当性がなかったり、社会通念上不当であったりするものはカスハラです。
カスハラには毅然(きぜん)とした態度で対応することが大切です。
カスハラであると判断する基準
カスハラとクレームの違いを踏まえると、カスハラを判断する基準として、以下の二つの視点が挙げられます。
- 要求内容の妥当性
- 手段・態様の社会通念上の相応性
要求内容の妥当性
例えば、介護サービスを提供している顧客から、「○○さんと同じサービスを自分にも提供しろ」と執拗に要求されたとします。しかし、この顧客との契約上、○○さんと同じサービスは提供できません。
この場合、顧客が要求するサービスを提供できない理由は契約内容であり、企業側に過失はありません。契約外の執拗な要求は妥当性に欠けるため、カスハラと判断してよい例です。
手段・態様の社会通念上の相応性
カスハラに当たる行為としてよく見られるのが土下座の要求です。土下座は謝罪の手段として社会通念上の相応性がありません。
また、従業員を長時間拘束してのクレームも業務に支障が出るため、社会通念上の相応性に欠けるといえます。これらもカスハラと判断できます。
このように、二つの視点からカスハラかどうか判断しましょう。
企業がカスハラの判断基準を定める際のポイント
カスハラとクレームの区別は法令では定義されていないため、企業が判断基準を設ける必要があります。前述の「要求内容の妥当性」と「手段・態様の社会通念上の相応性」の2点を意識して基準を設けておくと、現場で適切な対応ができるでしょう。
例えば以下のような基準が考えられます。
| カスハラに該当する | 理由のない慰謝料の請求 |
| カスハラに該当しない | 正当な理由のある商品の返金 |
なお、業種によっては、自社の商品・サービスに過失があるのか判断しにくく、クレームの悪質性を判断しかねる場合もあるでしょう。また、顧客第一主義の企業文化である場合は、著しい暴言や脅迫ではない限りはカスハラとしない企業もあります。
そのため、自社の業種や企業文化などに応じてカスハラの判断基準を定めることが重要です。
企業がカスハラ(カスタマーハラスメント)対策を行わないリスク
カスハラが社会的な問題となり、企業はカスハラ対策を行う必要に迫られています。カスハラ対策を怠るとどのようなリスクがあるのか解説します。
さまざまな問題の発生
カスハラを放置していると、以下のような問題が発生しかねません。
- 生産性の低下
- 従業員の休職・離職
- 業績の悪化
生産性の低下
カスハラの被害に遭った従業員は「私のせいでお客様を怒らせてしまった」などと思うようになり、自身の仕事に自信を持てなくなります。
また、暴言や脅迫などのストレスによりモチベーションが維持できず、パフォーマンスが下がってしまいます。
このようなカスハラの被害者が増えれば、企業全体の生産性低下につながりかねません。
従業員の休職・離職
カスハラを受けると多大な恐怖や悲しみなどの感情に襲われ、従業員は大きなストレスを感じます。
ストレスが原因となり心身の不調を招いて、休職や離職につながることもあります。休職者や離職者が多くなると社内の人手不足を引き起こし、業務に支障をきたす可能性も考えられます。
業績の悪化
カスハラ対策ができていないと世間に認知されると、「従業員を大切にしない会社」「顧客の言いなり」といった企業イメージが根付いてしまいます。
また、誹謗中傷を放置していると「あの会社の商品は不良品ばかりだ」「接客態度が悪い」など、事実に反する評価が広まることもあります。その結果、業績にも悪い影響が及びかねません。
このような問題が発生すると企業にとって大きな損失を招くため、適切なカスハラ対策が必要です。
企業責任を問われるケースも
カスハラ対策を行っていないと、従業員がカスハラの被害を受けた際に企業責任を問われるケースもあります。
労働契約法第5条[6]では、使用者(企業側)に労働者の安全配慮義務が定められています。
カスハラ対策を怠ると、企業側は労働者が安全に働ける環境づくりをしていないと判断され、法令違反とされる可能性があります。
カスハラ(カスタマーハラスメント)に関する法令
カスハラは社会問題として認識されており、国や自治体が法整備や条例制定を進めています。ここでは、カスハラに関する法令についてご紹介します。
【2025年4月施行】東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
2024年10月4日、東京都議会で「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が可決・成立しました。
今までカスハラに焦点を当てた法律は存在しておらず、条例の制定は東京都が全国初となります。また、東京都以外でも三重県桑名市や埼玉県、北海道などが同様の条例制定を検討しています。
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例のポイント
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(以下「東京都カスハラ防止条例」とします)について、事業者側が知っておくべきポイントを解説します。
三つの基本的な考え方
東京都カスハラ防止条例は、以下の三つの考え方を基本的な柱としています。
・「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」として、カスタマーハラスメントの禁止を規定
・「カスタマーハラスメント」の防止に関する基本理念を定め、各主体(都、顧客等、就業者、事業者)の責務を規定
・「カスタマーハラスメント」の防止に関する指針を定め、都が実施する施策の推進、事業者による措置等を規定引用元:産業労働局「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方」,2024年7月公表,p5(閲覧日:2024年12月18日)
カスタマーハラスメントの禁止に加え、顧客や就業者・事業者の果たすべき責務、カスハラ防止に必要な対応についても規定されていることがポイントといえるでしょう。
事業者の責務
事業者の責務については、努力義務として下記の内容が示されています。
- 就業者がカスハラを受けた場合、速やかに就業者の安全を確保し、カスハラを行った顧客に適切な措置を講ずること
- カスハラ防止のために必要な体制の整備、カスハラを受けた就業者への配慮、カスハラ防止のための手引の作成その他の措置を講ずること
罰則は明記されていない
東京都カスハラ防止条例では、カスハラ防止について努力義務を課しているものの、罰則は設けられていません。
罰則を設けていない理由について、東京都は以下のように回答しています。
Q.条例には、なぜ罰則がないのか。
罰則を設ける場合、刑罰の対象となる行為を厳格に定める必要があり、その結果、禁止されない行為はしても良いとの理解が広がる懸念があります。また、刑罰は最も厳しい法的な制裁であり、それ自体は決して望ましいものではないことから、防止の啓発に重点を置いた条例としています。
Q.罰則がないと実効性がないのではないか。
条例には罰則はありませんが、行為によっては、傷害罪、強要罪、名誉棄損罪などの犯罪に該当する可能性があり、刑法等に基づき処罰されるものと考えています。
引用元:東京都産業労働局「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 Q&A」,p1-2(閲覧日:2024年11月12日)
東京都では今後、カスハラ防止に関するガイドライン(指針)やマニュアルの策定が行われる予定です。企業はこうした指針を参考にしつつ、責務を果たす対応が求められます。
厚生労働省「パワハラ指針」
2022年6月1日から適用されているパワハラ指針(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)は、職場のパワーハラスメントに関する指針です。
この指針の中にはカスハラに言及している部分があります。カスハラを「顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)」と定義し、企業が行うべき対策として以下のような取り組みを示しています。
- 相談先(上司など)の周知、相談対応者の教育
- 悪質な顧客に一人で対応させないなど、カスハラ被害者への配慮
- カスハラ対応マニュアルの整備や研修の実施
厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)【令和2年6月1日適用】」(パワハラ指針)
カスハラ対策を企業に義務付ける方針
厚生労働省はカスハラ対策に関する有識者検討会を設置し、カスハラ対策の強化や法整備について検討を行っています。
2024年7月には従業員をカスハラから守る対策を行うよう企業に義務付ける方針を示しており、2025年、通常国会での関連法改正案提出を目指しています。
労働契約法における「安全配慮義務」
労働契約法第5条では、使用者(企業側)が労働者の生命や身体などの安全を確保して働けるよう「安全配慮義務」が定められています。
例えば、従業員が顧客からの誹謗中傷を受けた際、企業側がその事実を知りながら放置したことで、従業員が精神的な病にかかったとします。その場合、企業側は従業員を守るための適切なカスハラ対策を行っていないとされ、安全配慮義務に抵触すると考えられます。
こうした場合、カスハラの被害を受けた従業員に損害賠償請求をされる可能性があります。
e-GOV「労働契約法」
刑法・軽犯罪法
- 暴行罪
- 脅迫罪
- 強要罪
- 侮辱罪
- 威力業務妨害罪
- 不退去罪 など
企業が行うべきカスハラ(カスタマーハラスメント)対策
企業はカスハラ対策として、どのような対応を行えばよいのでしょうか。事前準備とカスハラ発生後の対策に分けて具体的に解説し、厚労省のマニュアルもご紹介します。
カスハラ発生を想定した事前準備
カスハラの発生に備えて、適切に対応できるよう組織体制を整えておくことが重要です。具体的には、以下のような取り組みを行うとよいでしょう。
カスハラの判断基準や対応方針の明確化
顧客の言動がカスハラかどうかを判断し、対応方法を考えることは、従業員にとって難しく負担の大きいものです。そのため、企業側がカスハラの判断基準を明確化し、対応方針を定める必要があります。
対応方針を定めるだけでなく、従業員に対する周知・啓発を行うことも重要です。企業がカスハラへの対応方針を明確に示すことで、従業員は安心して働けるようになり、トラブルの再発防止にもつながります。
相談対応体制の整備
従業員がカスハラを受けた際すぐに相談・対応できるように、相談対応者を決めたり、相談窓口を設置する必要があります。判断基準や対応方針と同様に、相談先も従業員に周知することが重要です。
対応方法・手順の策定
カスハラ対応に関するマニュアルを作成し、対応体制や方法を決めておきます。例えば、以下に関する内容です。
- 現場での初期対応の方法や手順
- 内部手続きの方法や手順
従業員への教育・研修
社内のカスハラに関する判断基準や対応方針などが定まったら、従業員に対し教育を行います。
中でも相談対応者は状況把握や相談者のフォローなどが必要なため、教育が大変重要です。カスハラを受けた従業員への配慮やプライバシーへの配慮など、定期的に研修を実施し、重点的に教育を行いましょう。
実際に、研修による効果も証明されています。日本労働組合総連合会による「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」[7]では、カスハラの被害を受け「仕事をやめた・変えた」という人のうち、企業がカスハラ対応に関する研修を行っていたのは8.5%、研修を行っていなかったのは67.6%と、59ポイント以上の差がついています。
カスハラ対策の研修を受けた従業員が離職する割合は、受けていない従業員と比べて非常に小さいといえるでしょう。
\「カスタマーハラスメント」対策コースを含む多様なラインナップ/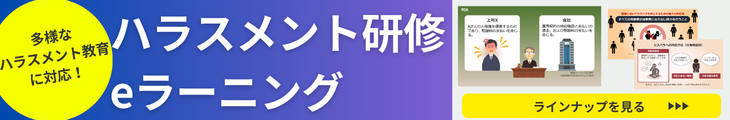
実際にカスハラが起こった際の対応
もしカスハラが発生してしまった際は、以下のような対応が必要です。
事実関係の正確な確認と対応
カスハラに該当するかを判断するために、顧客や従業員の証言・証拠に基づいて正確な事実を確認します。
瑕疵(かし)や過失がある場合は謝罪や商品交換・返金などの対応を行いますが、瑕疵や過失がない場合は要求に応じません。責任者からカスハラの行為者へ帰ってもらう旨を伝える、出入り禁止を通告するなど、あらかじめ定めた手順に沿って行動します。
従業員への配慮の措置
被害を受けた従業員に対し、適正な配慮を行います。
顧客から従業員を引き離す、警察や弁護士に相談するといった安全確保に加え、メンタルヘルスの不調が見られる場合は専門家に相談しアフターケアを行うなど、精神面への配慮も必要です。
再発防止の取り組み
再発を防ぐため、取り組みの定期的な見直しや改善を行います。従業員への事例共有や勉強会なども再発防止に効果的です。
上記以外にも、必要と思われるカスハラ対策の取り組みを従業員からヒアリングして追加していくとよいでしょう。
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
上記の内容は、厚生労働省が2022年に公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を参照しています。企業が取り組むべきカスハラ対策の内容を取りまとめたもので、基本的なカスハラの例や対応の仕方、カスハラ対策の重要性、カスハラ対策のポイントなどを知ることができます。
このマニュアルの作成にあたっては、顧客に接する機会の多い小売、運輸、飲食サービス業などの企業12社にヒアリングが行われており、実際のカスハラ例や対策の好事例も掲載されています。ぜひ活用しましょう。
カスハラ(カスタマーハラスメント)対策が効果を発揮した企業事例
効果的なカスハラ対策を行った企業事例として、2社をご紹介します。
JR東日本:カスハラを行う客に「対応しない」方針を策定
JR東日本グループは2024年4月に「JR東日本グループカスタマーハラスメントに対する方針」を策定し、対応方針に「カスタマーハラスメントが行われた場合には、お客さまへの対応をいたしません」と明記しました。
カスハラを行う乗客には「対応しない」ことを明確に示した上で、悪質と判断される行為に対しては、警察・弁護士等のしかるべき機関に相談・厳正に対処するとしています。
方針策定から3カ月後の社長による定例会見では、「対処方針を明確にしたことで、乗客の対応にあたる社員が上司とともに組織的に対応しやすくなり、安心して働けるようになった」と一定の効果が見られたことを示しています。
freee株式会社:カスハラの対象となる行為や対応方針を社外向けに発信
freee株式会社は、従業員、パートナー企業(業務委託先企業を含む)が安心して顧客と接点を持つことを目的として、2023年2月9日より「カスタマーハラスメントに対するfreeeの考え方」を公開しています。
「カスタマーハラスメントに対するfreeeの考え方」では、カスハラの「対象となる行為」、「社内対応」、「社外対応」について明記し、カスハラがあればサービスやサポートの提供を断る場合があるとしています。
また、社内ではカスハラ対応用のガイドライン作成・運用を行い、全従業員が参加する会議や社内SNS等を利用して周知を行いました。これらの取り組みは社内外でさまざまな反響を呼び、従業員から「安心できる」という声が届くなどの成果につながっています。
まとめ
カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、顧客や取引先からの著しい迷惑行為をいい、暴言・暴力のほか、土下座の強要や性的・差別的な言動も該当します。
クレームとカスハラを区別する基準として、以下のポイントを意識しましょう。
- 要求内容の妥当性
- 手段・態様の社会通念上の相応性
この2点を基準に、自社に合った判断基準を設けておくことで、現場が混乱せずに対応できます。
カスハラ対策をしない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 生産性の低下
- 従業員の休職・離職
- 業績の悪化
また、国や自治体はカスハラ対策のための法整備や条例制定を進めており、企業はカスハラ対策によって従業員の安全を守る必要性が高まっています。
この機会に、自社におけるカスハラとクレームの判断基準を確認し、カスハラ対策の内容を見直してみてはいかがでしょうか。
\後で読み返しできるハラスメントの解説資料はこちら(無料)/
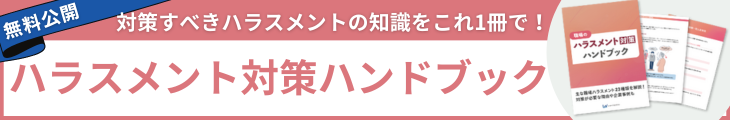
[1] 東京都産業労働局「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(閲覧日:2024年11月12日)
[2] 厚生労働省「第10回雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」,2024年10月3日公表,(閲覧日:2024年12月18日)
[3] UAゼンセン「『カスタマーハラスメント対策アンケート調査結果』記者レクチャー資料」,2024年6月5日公表,p3(閲覧:2024年11月12日)
[4] 東京商工リサーチ「『企業のカスタマーハラスメント』に関するアンケート調査」,2024年8月27日公表(閲覧日:2024年11月22日)
[5] 厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)」,2024年6月公表,p7.8(閲覧日:2024年11月12日)
[6] e-GOV「労働契約法」(閲覧日:2023年5月9日)
[7] 日本労働組合総連合会「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」(閲覧日:2023年5月25日)
参考)
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」,https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf(閲覧日:2023年4月18日)
厚生労働省「『職場のハラスメントに関する実態調査』の報告書を公表します」,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40277.html(閲覧日:2024年12月18日)
日本労働組合総連合会「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」,https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20221216.pdf?32(閲覧日:2023年4月18日)
池内裕美「なぜ『カスタマーハラスメント』は起きるのか-心理的・社会的諸要因と具体的な対処法」,『情報の科学と技術』,70巻,10号,2020,p486-492.
厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)【令和2年6月1日適用】」,https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf(閲覧日:2023年4月18日)
e-GOV「労働契約法」,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128 (閲覧日:2023年5月9日)
香川総合法律事務所「カスハラとは?カスタマーハラスメントとクレームの違いをわかりやすく図解」,『カスハラ対策相談ナビ』, https://customer-harassment.com/kasuhara-claim-distinction/(閲覧日:2023年4月18日)
ロア・ユナイテッド法律事務所「カスハラとは何か?会社が気をつけることは?」,https://www.loi.gr.jp/law/law_qa-3831/(閲覧日:2023年4月18日)
TOKYO MX+「SNSでカスハラ増…スマホ利用のモラルどう植え付ける?」,https://s.mxtv.jp/tokyomxplus/mx/article/202208010650/detail/(閲覧日:2023年5月23日)
厚生労働省「カスタマーハラスメントへの取組により従業員の安心感を獲得!」,『あかるい職場応援団』,https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/customers-measures/archives/2(閲覧日:2024年11月12日)
厚生労働省「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会 報告書 ~女性をはじめとする全ての労働者が安心して活躍できる就業環境の整備に向けて~ 」,2024年8月8日公表,https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001285696.pdf(閲覧日:2024年11月14日)
産業労働局「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(新設)」,https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/09/11/documents/18_01.pdf(閲覧日:2024年11月14日)
桑名市「市長定例記者会見」,2024年4月5日公表,p35,https://www.city.kuwana.lg.jp/documents/1433/pawapo4545.pdf(閲覧日:2024年11月22日)
埼玉県議会「令和6年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(水村篤弘議員)」,2024年10月23日公表,https://www.pref.saitama.lg.jp/e1601/gikai-gaiyou/r0609/r0609-4/b/0100.html(閲覧日:2024年11月22日)
北海道議会「北海道カスタマーハラスメント防止条例(仮称)に関する意見募集の実施結果について」,https://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/gaiyou/201075.html(閲覧日:2024年11月22日)
東日本旅客鉄道株式会社「カスタマーハラスメントに対する方針」,『JR東日本』,https://www.jreast.co.jp/company/customer-harassment/(閲覧日:2024年11月22日)